(電子ブック)
保険内容・月額掛金の詳細など、こちらからご確認ください。

共済・福利厚生
従業員の働く環境を守り
会社をよりよく、元気よく。

死亡・障害・入院を
いつでも保障※1
死亡保険金
最大3,000万円
まで保障※2
会議所独自の
見舞金・祝金を給付
医師の診査が不要
健康状態について
簡単な告知が必要です
配当金として還元※3
2024年度 支払配当実績
45.97%
<保険期間2025年12月1日~2026年11月30日>
| 保険年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 15~35歳 | 996 | 849 |
| 36~40歳 | 1,074 | 972 |
| 41~45歳 | 1,203 | 1,041 |
| 46~50歳 | 1,416 | 1,197 |
| 51~55歳 | 1,737 | 1,383 |
| 56~60歳 | 2,193 | 1,575 |
| 61~65歳 | 2,979 | 1,872 |
| 給付内容 | 給付金額 3口の場合 |
|---|---|
| (病気等による)死亡保険金 | 300万円 |
| (病気等による)高度障害保険金 | |
| (不慮の事故または所定の感染症による) 死亡保険金+災害保険金 | 300万円 + 300万円 |
高度障害保険金+障害給付金 | |
| (不慮の事故により第6級~第2級の障害状態になったとき) 障害給付金 | (障害の程度により) 30~210万円 |
| 不慮の事故による入院給付金 | (1日につき)4,500円 |
| 給付の内容 | 給付金額 3口の場合 |
|---|---|
| 病気入院見舞金 | 10,000円 (口数に応じて10,000~50,000円) |
| 事故通院見舞金 | |
| 結婚祝金 | 一律 10,000円 |
| 出産祝金 | |
| 二十歳祝金 |
従業員が休日にケガをした。5日間入院し、その後通院5日間
災害入院給付金 22,500円
+事故通院見舞金 1万円
従業員が病気で死亡
死亡保険金 300万円
従業員がめでたく結婚・出産!
結婚祝金 1万円
+出産祝金 1万円
(1)お電話(03-3283-7905/平日9:30~17:00)または「お問い合わせフォーム」より、東京商工会議所共済センター・生命共済担当へご連絡ください。
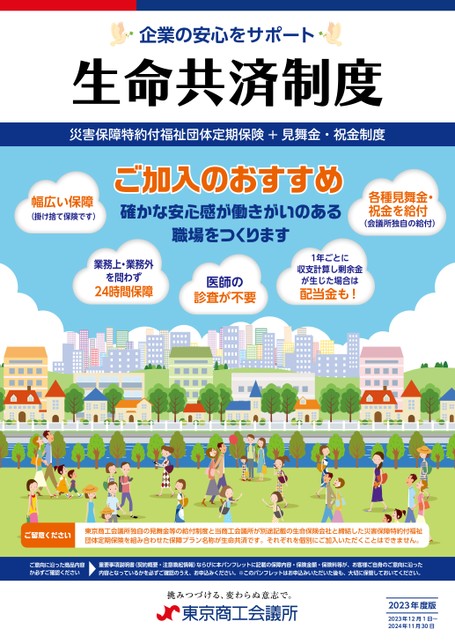
保険内容・月額掛金の詳細など、こちらからご確認ください。
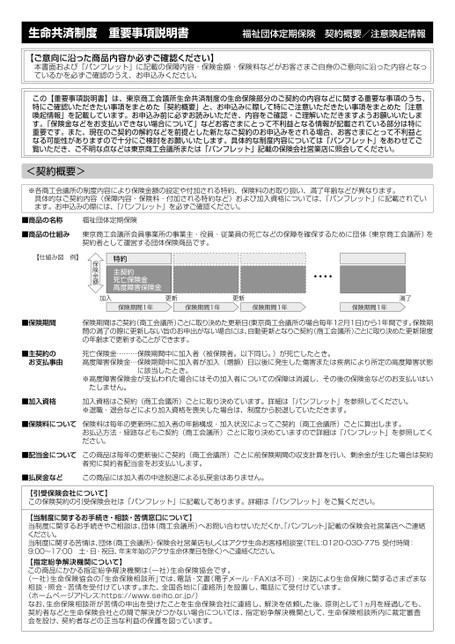
<パンフレット記載内容>
個人事業主のみの加入はできます。但し、個人事業主がご自身のために負担した掛金は、本共済制度の「特約部分の保険料」および「制度運営事務費」を除いた金額、また配当金がある場合は、この配当金も差し引いた金額が所得税法上、生命保険料控除の対象となります。なお、個人事業主が、従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。
できます。但し、掛金は事業所口座からの引去りとなりますので、事業所が対象加入者の掛金を毎月集金していただき、引去り日の前日迄に事業所口座に入金ください。
下記WEBフォームから、ご申請をお願いします。
なお、ご加入時のご契約内容により、事業所受取と本人(加入者)受取に分かれますのでご注意ください。
個別にお手続きをご案内いたします。生保共済担当(03-3283-7905)までご連絡ください。
所定の書類をお送りいたします。
退院後、180日以内に通院を開始していれば(5日以上通院した場合)見舞金の対象となります。見舞金請求書に医師の証明か、もしくは、通院証明書または領収書のコピー(5日以上の通院日数がわかるもの)を添付の上、ご請求ください。
不慮の事故とは業務内外を問わず急激かつ偶発的な外来の事故で、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類によっています。スポーツによる腱鞘炎、筋肉痛などのスポーツ疲労は対象となりません。詳しくは、「生命共済制度」のしおりの25ページに掲載しておりますので、ご確認ください。
業務内外にかかわらず5日以上の入院及び障害が残った場合に、それぞれ入院給付金・障害給付金の対象となります。
但し、労災認定の障害等級と生命共済の傷害等級による給付割合が異なっているので、必ず、しおりの給付金割合表をご確認ください。
生命共済制度のしおりに掲載しております「見舞金・祝金給付」に関する運営要領第12条または「請求手続きについて」の「支払わない場合」をご覧ください。病気入院の場合、人間ドックなどの検査入院、通常出産による入院は給付の対象外です。それ以外の一般に病気と判断される治療で、継続して5日以上入院した時は、入院証明書、領収書のコピー(入院期間のわかるもの)が添付いただければ対象となります。
支給されます。夫婦それぞれに請求する権利がありますので、それぞれ祝金請求WEBフォームからご申請をお願いします。
※見舞金・祝金の請求申請は、請求事由発生から3年以内とします。
毎年10月上旬には作成していますので必要な場合にはお申し出ください。なお、全加入者にお送りしているのではなく、お申し出いただいた方(掛金個人負担の場合のみ)にお送りしています。
保険期間は1年で毎年12月1日~翌年11月30日までです。したがって、期間途中での解約は対象外となります。(満了月11月30日解約の事業所についてはその年度の配当金をお支払いします)
解約される際は下記の解約通知書を入力の上、印刷・捺印をし共済センターまで送付をお願いいたします。
(生命共済制度を解約される事業所のみ閲覧・ダウンロードできます。パスワードは共済センターにお問い合わせ下さい)
脱退の際の異動日(脱退日)については、東商が不備なく本帳票を受理した月の末日となります。(脱退日は当月末日の記入をお願いします)
なお、東商が遡及脱退を認める場合は当月25日(休日の場合は前営業日)までに、不備なく本帳票を受理した場合のみ前月末日として脱退手続きが可能です。それ以上の遡及脱退はできません。
例)6月末日脱退日へ遡及を認める場合…7月25日までに東商が不備なく本帳票を受理する。
下記「加入取消通知書」を東京商工会議所へご提出いただきます。お電話(03-3283-7905/平日9:30~17:00)または「お問い合わせフォーム」より、東京商工会議所共済センター・生命共済担当へご連絡のうえ、パスワードや詳細な手続きをご確認ください。
各制度は連動しておりませんので、それぞれで必要な手続きをおとりください。