持続可能な社会の実現には、「教育」が不可欠です。SDGs(持続可能な開発目標)達成目標年(2030年)までの折り返し地点にあるいま、知識やスキルに加え、持続可能な社会の実現に向けた価値観や行動を育むための「教育」が求められています。今回は「教育」をテーマに有識者にお話を伺いました。
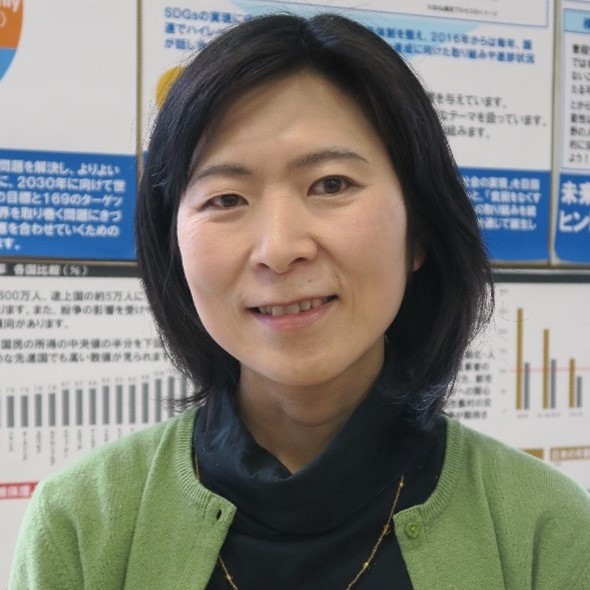
星野智子(ほしの・ともこ)氏
環境パートナーシップ会議副代表理事。2003年より地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)の運営に参加。現在、SDGs市民社会ネットワーク理事、海外環境協力センター理事、日本自然保護協会評議員、日本サステナブル・ラベル協会監事、農業体験企画「土の学校」主宰など、多岐の市民活動にかかわる。2012年SDGs策定プロセスが始まって以降、SDGsをテーマとした講演や普及活動を行う。

葭内ありさ(よしうち・ありさ)氏
博士(社会科学)。お茶の水女子大学附属高等学校教諭、同大学非常勤講師、同大学エシカル・ラーニングラボ代表。お茶の水女子大学卒業、同大学院修了。慶應義塾大学法学部卒業。家庭科でサステナブル、サイエンスを題材とした授業創りや、国内外のエシカル消費の研究・啓発に取り組む。消費者庁「倫理的消費調査研究会」委員等歴任。文科省検定教科書(東京書籍)編集委員。NHK高校講座「家庭総合」監修・講師。
<目次>
2030年まであと7年、SDGsは達成できるか繰り返し学び、エシカル消費を定着
2030年まであと7年、SDGsは達成できるか
SDGsの広がりとともに、エシカルやサステナビリティ(持続可能性)への関心が高まり、受け入れ方が柔軟になってきました。社会全体のコンセンサスが取れ、企業の意識も変わり、一体となってSDGsの達成に向かっていることは非常に意味があると思います。
「SDGsに関する生活者調査」(2023年、電通)によると、SDGsの認知率は9割超に上りました。「内容まで含めて知っている」と回答した人は4割に増え、なかでも10代の若者の過半数は説明までできるという段階になっています。
次の課題は「実行性」です。10代は知識がある一方で、「実際に行動したいか」という問いになると、いきなり実践意欲が下がってしまうのです。行動が伴わなければ、社会は変わりませんので、どのように行動につなげていくかが、ネクストステージです。
――6月に発表された「持続可能な開発報告書2023」は、このままのペースでは目標全体の2割も目標を達成できないと指摘しました。 「知識と行動のギャップ」はどのように解消していけるでしょうか。
一方で、世界的にも、SDGsに関係する教育を行っている割合は7%にとどまるという研究結果もあります。ですから、教育の現場でもできることはまだまだあると思います。

持続可能な社会づくりには、教育がカギを握る
――星野さんは、地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)などで、環境教育や環境に関する情報発信をされてきました。SDGsの進捗をどのように評価されていますか。
国際機関や政府、民間企業も多額の資金を拠出しているものの、社会の在り方や人の行動を変革するのは、そう簡単ではありません。新型コロナウイルス感染症の世界的流行、ウクライナやパレスチナ・ガザ地区での戦争の影響は大きく、SDGsが進まなかったことは、非常に残念です。
また、若い世代には「気候不安症」が広がっていると聞いています。気候変動に不安や罪悪感を覚え、メンタルヘルスの問題を抱えている子どもたちが増えているようです。私は長年、環境活動を続けてきましたが、次世代にツケをまわしてしまっていることを、とても残念に感じています。
私たちがどのように持続可能な社会に「変革」できるのかが、問われています。
繰り返し学び、エシカル消費を定着
――国連の「持続可能な開発のための教育(ESD)の10年」(2005―2014年)をきっかけに、日本でESDの概念が広まりました。教育の在り方や学生の意識はどのように変わってきたでしょうか。
以前から、エシカル消費を定着させるには、幼少期からスパイラル(らせん)状に繰り返し学ぶことが有益であるとの考えを抱いていました。
お茶の水女子大学には、1つのキャンパス内に隣接して保育所や幼稚園から、小中高、大学、大学院まですべてあります。そこで、高校1年生が、チョコレート生産における児童労働について小学5年生に教えたり、高校2年生がエシカル消費全体について中学1年生に教えたりするような仕掛けをしています。
学んで知識を得ることも大切ですが、人に伝えたときに、初めて「自分ごと化」できるのではないでしょうか。小学生も熱心にいろいろ質問をしますので、高校生も刺激を受けています。
お茶の水女子大学は2022年4月、SDGs推進研究所を設立し、全学でフードドライブを実施しています。昨年、先にフードドライブについて学んだ小学校6年生が、今年の高校1年生に教える授業もありました。
小学生にとって、年上のお姉さんたちに教えるのは、とてもドキドキすることです。小学生にとっては人に伝える勉強になりますし、高校生も一生懸命な小学生の様子に真剣に耳をかたむけます。
教え合うことは、お互いにとって大きな学びになります。このように、ぐるぐると「学びの連続性」をつくりたいと思っています。
GEOCは、いわゆる環境・サステナビリティの学習施設として、ウェブサイトも活用しながら関連の情報発信をしています。「みんなで考えながら仕組みを作っていきたい」という思いで、さまざまなワークショップやセミナーなどを行ってきました。

GEOCでは、キリバスのNGOを招いて気候変動の勉強会を行った
いまの高校生は、性別にかかわらずジェンダー課題への関心も高いようです。
女性のリーダーシップと気候変動政策の成果を調査した論文(豪カーティン大学)では、女性の議会代表が多い国ほど国際環境条約を批准する傾向が強いことが分かりました。環境問題とジェンダー課題をクロスオーバーさせた情報発信などにも、今後は力を入れていきたいと考えています。
――SDGsの目標は、単独で存在しているわけではなく、それぞれが関連し合っているということですね。
例えばジェンダー課題のなかにも、労働環境や賃金の男女格差、早すぎる結婚(児童婚)、女性のエンパワーメント、LGBTQなど、さまざまな観点があり、それらはエシカル消費や環境破壊の話にもかかわってきます。こうしたつながりを意識することが大切です。
私は水引(みずひき)のピアスを愛用しているのですが、こうした伝統工芸品もエシカル消費の1つです。海外で作られたフェアトレードの商品を買うだけが、エシカル消費ではありません。
日本の伝統工芸品を使ったり、その土地のものを取り入れたりすることは、伝統技術や産業を守ることにもなりますし、CO2排出量も抑えられます。「買う」だけではなく、「買わないこと」「使わないこと」もエシカル消費です。英ファッションデザイナーのステラ・マッカートニーさんは、洗濯回数を減らすことを呼びかけています。
私自身も「自分発」ということを大事にして、世界と自分はつながっているということを伝えるようにしています。例えば、スマートフォンやTシャツのように身近なアイテムを題材にして、児童労働や森林破壊、ジェンダー、教育、福祉、エネルギー問題といったそれぞれのイシューがつながっていることを伝えています。
それでも、講演だけで伝えるのは限界があり、やはり体験が大事です。「聞いたことは忘れる、見たことは理解する、体験したことは身に付く」と言われますが、この三段論法で、いかに「自分ごと化」できるかに注力していきたいです。
eco検定は、環境と経済を両立させた「持続可能な社会」の実現に向けて、環境に関する幅広い知識を身につけ、環境問題に積極的に取り組む「人づくり」を目的に2006年に創設されました。ビジネスパーソンから次代を担う学生をはじめとする、あらゆる世代の方が受験し、受験者数は延べ60万人、合格者(=エコピープル)も36万人を超えています(2023年8月末現在)。
「合格して終わり」ではなく、検定試験の学習を通じて得た知識を「ビジネスや地域活動、家庭生活で役立てる=現実の行動に移す」ことを促しています。毎年、エコピープル等の活動を表彰する「eco検定アワード」等も開催。
eco検定の詳細はこちら
【関連記事】
「地球にやさしい」は使えない? 「グリーンウォッシュ」規制強化へ気候変動に続き、進む生物多様性の情報開示
AIはサステナブルな社会の実現にどう貢献できるのか
知っておきたい2023年度のサステナビリティ・トピックス





