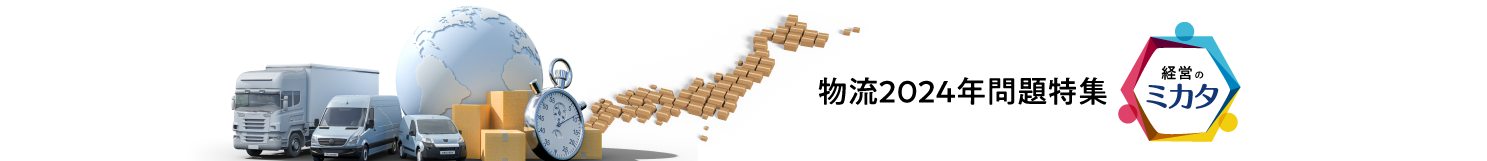更新日(事例掲載日):2025年3月7日
昌和興産株式会社
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング9F |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 齋藤 隆之 |
| 資本金 | 3,600万円 |
| 従業員数 | 13名 |
| 設立年 | 1975年 |
| 企業HP | https://www.showakosan.com/ |

昌和興産株式会社
1975年に株式会社ニフコの正規代理店(一次販売店)として創業し、2025年に設立50周年を迎えた工業用ファスナーメーカーの「昌和興産株式会社」。
工業用ファスナーとは、主に工業製品のパーツを締め付けたり、接合したりするための部品のことである。同社はプラスチックファスナーや留め具などの樹脂部品を中心に、自動車向けの消耗部品や、海外向けには自動車のアフターメンテナンス用部品等を販売しており、東京都豊島区池袋、栃木県宇都宮市、大阪府吹田市に営業拠点を置く。
物流改善に向けた
取組み内容
■運送料の値上げに備えて危機管理を図る

荷役の補助のために台車を増加
国内の約500社とBtoB取引を行い、池袋、宇都宮、大阪の3拠点から製品を配送している昌和興産株式会社。例えば池袋にある東京営業所では、1,500種類ある製品の中で常時200種類もの在庫を用意している。ひとつひとつがごく小さな部品であることから受注は主に1,000個単位で、配送は運送会社へ委託。「月曜から金曜まで毎日20~30件ほどの出荷があり、段ボールの大きさや個数は顧客によってさまざまです」と齋藤隆之社長は語る。
運送会社は2社を採用し、1社限定は避ける
出荷作業を行う一方で、在庫確保のためにニフコから製品を入荷する手配も必要だ。毎日ではないものの定期的に荷物を受け取っていることから、運送会社は同社にとってパートナー的存在である。そのため、利用する運送会社は信頼できる大手2社に限定。「製品の性質上、荷物の個数が大きく変動することはないですし、BtoB取引なので再配達のわずらわしさもない。運送料は常に安定しています」と齋藤氏は話す。
2024年4月にドライバーの拘束時間や休息期間、運転時間等の基準を定めた法律「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」が改正されたが、今のところ、運送料の大きな値上げは発生していないという。齋藤氏は「2社に委託している背景には、危機管理の目的があります。1社に絞れば、値上げを持ちかけられたときに条件を飲むしかない。しかし、2社であれば料金の比較ができるし、別の方法を探る時間の余裕もあるでしょう」と説明する。
ドライバーとの信頼関係構築にも注力
数ある運送会社の中から2社に限定していることにより、運送会社と良好な関係を築きやすいメリットもある。顔見知りのドライバーとの定期的なコミュニケーションが、信頼関係の構築につながるためだ。とりわけ「物流2024年問題」によってドライバーの過酷な労働環境を認識した同社の社員たちは、ドライバーに対してより深い感謝の気持ちを抱くようになったという。「ドライバーが来ると、『お願いします』と丁寧に挨拶するようになりました。この一言があるだけでお互いの距離が縮まり、日々のお付き合いや交渉などがしやすくなりますね」と齋藤氏は実感している。
それだけではなく、可能な範囲で出荷時の荷物の積み込み補助を行うことで、少しでもドライバーの稼働時間を短縮するという取り組みも行っているという。荷主は運送会社にとって大切な顧客であることから、一般的に“上の立場”と捉えられることも多い。しかし、昌和興産では顧客に荷物を届ける使命を持つ同じ立場の“同志”として、リスペクトの気持ちを持ってドライバーと接している。こうしたほんの少しの心がけこそが信頼関係の構築につながり、危機管理としてもしっかりと機能しているのだ。
■出荷の遅れは顧客に丁寧に説明し、理解を促す

搬入作業の補助も行う
集荷・到着時間が不定期になり、その日の出荷は困難に
先述のように、法改正後に運送料の値上げはなかったものの、配送時間や集荷時間は多少見直されたという。「一定だった荷物の集荷時間や到着時間が不定期になるケースがあり時間が読み難くなりました。それまでは午前中に集荷が来て、その日中に出荷することも可能だったのですが…」と齋藤氏は振り返る。
昌和興産は最短で1~2日以内で出荷が可能な体制を整えていたが、この変更によって1日ほど出荷がずれ込むようになった。「とはいえ、大きな影響が出たかといえば、そうでもありません。当社はBtoB取引が主体で、各顧客から計画的に発注していただいているため、『すぐに製品が届かなくては困る』といったご要望は少ないからです」と齋藤氏は話す。 顧客には、荷物の到着が1~2日ほど遅れる可能性があることを丁寧に説明。「物流2024年問題」の認識が広がっていることもあり、どの顧客も理解を示してくれているという。
■3営業拠点で荷物をまとめて一括入荷し、運送料のコストダウンに
東京で10万個を仕入て、2拠点へ振り分けて配送
昌和興産では、3営業拠点に適切な量の在庫を確保することを何よりも重視している。在庫があることで安定した供給体制を整えることができ、速やかな出荷が可能となるためだ。そこで、同社が着目したのが「荷物の集約」である。
「以前は、ニフコから製品を入荷する際は3営業拠点でそれぞれ依頼していたのですが、それを1拠点でまとめて入荷することにしたのです。例えば、3拠点分10万個の製品を東京営業所で受け取り、それを数千個など必要な数だけ宇都宮と大阪の2拠点に振り分ける形です。東京営業所から各拠点に振り分けた分の配送料は高価になりますが、『数が多い分、安くしてもらえないか』と運送会社に交渉しました。逆に宇都宮営業所や大阪営業所がメインの製品に関しては、そちらで大量に仕入れて東京営業所へ振り分けています。このように在庫を社内全体で管理することで、各営業所が無駄な在庫を抱えることがなくなったほか、運送料の削減にもつながっています」と、齋藤氏は手応えを語る。
■在庫は2~3ヶ月ごとに確認。ただし課題も残る

大阪支社でもかご車を利用し荷役時間の短縮に協力
回転の早い製品は多く仕入れ、数の変動を管理
製品の在庫切れが発生することを避けるために、齋藤氏は定期的なチェックを欠かさない。在庫は過去2年ほどさかのぼり、製品ごとに売り上げ状況を把握。さらに2~3ヶ月ごとに発注数を見直す作業を行うことで、在庫切れを避けられるそうだ。齋藤氏は「入れ替わりの早い製品の場合、あえて在庫を多く確保しておくこともあります。『すぐに出荷できます』という付加価値を提供することで。仕入価格に対して適切な利益を上乗せできる場合もあります。そういったケースも踏まえながら、こまめに在庫数の調整を行っています」と語った。
ただし、在庫に関連した課題はいくつかある。「売上を100%在庫でまかなえれば、取引をスムーズに行えて理想的なのですが…」と齋藤氏。10数年前は在庫での売上がわずか5%だったが、現在は40%にまでに上昇している。「今後の目標は『50%』で、その達成に向けた施策として取り扱うアイテム数のスリム化(集約)を検討しています。例えばクリップだけでも数種類の在庫があるのですが、一例として最も売れている穴径8φ(8mm)の大きさの種類を増やすなど、売れやすい製品を中心に在庫を確保することを考えています」
また、齋藤氏は同社の「在庫回転率」にも課題を感じている。在庫回転率とは一定期間内に商品が入れ替わった回数を示す指標のことで、「製品の年間売上額÷平均在庫金額」で計算される。一般的には「10~15」ほどの在庫回転率を目標にする企業が多いが、昌和興産における2024年の在庫回転率は「8」だった。「当社の在庫金額は、平均で2,200万円ほどです。昨年は不調だったので『8』でしたが、在庫をうまくコントロールできれば回転率を上げていけると思います」と齋藤氏は意欲を見せた。
作業効率アップに向けて、広いスペースへの移転を検討中
在庫管理だけでなく、管理スペースにも課題は残るという。東京営業所はビルの9階にあり、ワンフロアに事務所と倉庫がある。「池袋という土地柄もあり、それほど広さもなく、在庫をこれ以上増やすことができません」と齋藤氏は嘆く。また、ドライバーが9階まで荷物を抱え、狭いエレベーターを行き来するのも効率が悪い。ビル1階への移転を考えたこともあるが、賃料が高価である上、物件が空く様子もないという。「地方に新たな物流拠点を設けることも検討していますが、実現までにはもう少し時間がかかりそうです。従業員やドライバーが気持ちよく働くためにも、しっかりと検討すべき課題だと考えています」と齋藤氏は語った。
昌和興産の理念は“係わる人すべてが幸福になる”ことだ。「自社だけでなく、仕入先や顧客など(運送会社も含めた)自社に係わるすべての人々に利益が行き渡り、どこか1つでも不利益になってはならない」という想いを貫いている。いくつかの課題はあるが、向かい立つ齋藤社長がその歩をゆるめることはない。