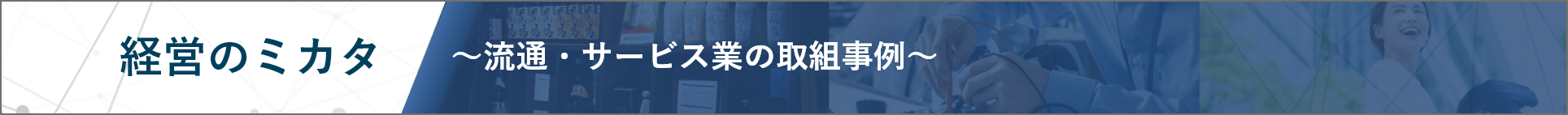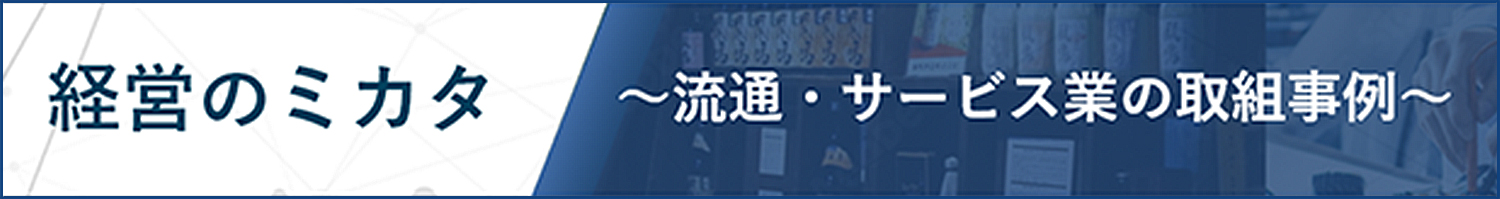2024年7月22日更新
株式会社ときわ
| 所在地 | 東京都台東区浅草1-3-3 |
|---|---|
| 代表者 | 牧 信真(代表取締役) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 21人 |
| 設立年 | 1922年 |
| 企業HP | https://tokiwa-syokudou.co.jp/ |

代替わりとともに改装した店内
株式会社ときわは、浅草・雷門のすぐ横に構える老舗食堂「浅草ときわ食堂」を中心に、割烹技術を用いた和定食を提供する食堂として1922年に創業、2022年に創業100周年を迎えた。
元々は、明治・大正時代に隆盛を誇った料亭・常盤花壇の食堂部門「ときわ食堂総本店」からのれん分けされる形で第5支店として独立し、昭和初期から戦後しばらくは東京都指定民生食堂として、戦後の復興を支える人々のために、“安く、ボリュームのある”料理を提供し続けてきた。
目指すのは他社と競合しない食堂
「浅草ときわ食堂」は東京都指定民生食堂だった歴史から、労働者に対して“安く、ボリュームのある”料理を提供する大衆食堂として、長年続いてきた。しかし、4代目代表取締役の牧 信真氏は「近年、低価格で食べられる同業態のチェーンの飲食店が台頭することによって、サラリーマンの顧客層が少なくなっていると感じていました。そうした時に、仮に近場に同業態のチェーン店が来た場合、大量仕入れや調理工程の機械化・マニュアル化によって大幅なコスト削減を行うチェーン店に対して、個店が安さと量で勝負しても負けると思ったのです」と語る。
そこで、思いついたのが、“和食”を武器にして売り出すことだった。「実は父の代で、割烹での修行経験をもとに、提供する料理の質を普通の食堂とは一線を画すレベルまで上昇させました。そのことを踏まえて、『浅草ときわ食堂』が顧客である庶民に提供できるものは何かを考えていた時に、実は庶民が本格的な和食に触れる機会はあまりないと気づいたため、和食を打ち出すことを決めました」と牧氏。そうして、“和文化を通じて日常をちょっと豊かにする”という料理方針を確立し、顧客である一般大衆層が普段触れることのない、本格に近い和食を提供するようになったという。「和食の要である魚に関しては代々経営者自ら市場に毎朝足を運びこだわりをもって仕入れています。多分、食堂でこれだけちゃんとした和食を食べられるところはほとんどないと思います」と牧氏は自負している。
“自称日本一”のアジフライ!

“自称日本一”のアジフライ
父の代での料理の質の向上に加えて、牧氏はメニュー数についても見直しを行った。「先代の時代くらいまでは、メニュー数は多ければ多いほど良いという方針でした。ただ、冷蔵庫のスペースは限られていますし、めったに頼まれない商品のために他の商品の提供が遅くなるということもあったので、効率性を考えて注文される頻度が低い商品については削減しました」と牧氏。
その代わりに、新たに取り組んだのが、“自称日本一”の「アジフライ」を作り上げることだった。ただ意外にも、アジフライに対して最初から強い思い入れがあったわけではないという。「“自称日本一”を掲げたのは、浅草の良さを聞かれたときに、何もないと自嘲するのではなく、我々個店が日本一のものを提供しているという気概を持つべきではないかと考えたからです。そこで、『浅草ときわ食堂』の目玉になり得るものを考えた時、“和食”が魚食文化であることに加え、魚に関しては代々経営者自ら市場に毎朝足を運び、こだわりをもって仕入れていたので、魚料理を打ち出そうと決めました。その上で、魚料理の中でも広く庶民に浸透しているということで、『アジフライ』を選んだのです」。
“日本一”を自称する以上、様々な点にこだわっているという。「一般的なアジフライは冷凍のメアジとパン粉を使用していますが、当社では魚の味を味わってほしいと思っているので、冷凍されていない生のアジに細かく砕いた乾パンをつけて揚げています。また、規格についても一定の厚み・大きさ以上のものを仕入れるようにしています」という。とはいえ、毎日同じ大きさのアジが市場に出るわけではないため、その日仕入れたアジの大きさによって提供価格が変動するそうだが、牧氏は「時価による値段の差を気にされるお客様はあまりいらっしゃらないと感じています。逆に、アジフライにこだわったことで、特にPRをしていないのにも関わらず、お客様の間で『おいしい』という口コミが広がり、呼び水として機能しています」と語っている。
ターゲット層に注目した価格転嫁

“随所にこだわりが見られる調理風景
値上げについても、2012年に牧氏が代表取締役に就任した当時から、ずっと考えていたという。「値上げにはコストプッシュによる値上げと、品質の上昇に伴った値上げの2種類があると考えています。その中で当社は、仕入れや調理方法にこだわることで品質は上昇しているにもかかわらず、顧客の反応を気に掛けるあまり、なかなか値上げに踏み切れていませんでした」と牧氏。「ただ、ここ数年、原油価格上昇等による物流コスト上昇の影響で仕入れコストが大幅に上がったことを契機に、コスト増加分の売価への価格転嫁と併せて、品質上昇分の値上げを進めています。また、コロナの影響で外食機会が減ったことにより、外食がただの食事ではなく特別な体験としての意味合いを持つようになったことで、人々が一回の外食体験にかける金額が上がるのではという考えもあります」。
しかし、価格転嫁を進める中でも常に意識していることがあるという。「観光客が注文することの多い定番商品については積極的に価格転嫁を進めてはいますが、常連客が頻繁に注文する日替わり定食に関しては、なるべくお客様の負担が小さくなるように値上げ幅は小さくしています。今も常連のお客様は多くいらっしゃるので、長くやっていると、昔ながらの人情は切れないということもあります。また、コロナ禍のように何か予想もつかないことが生じ、主要な顧客層の一つである観光客が減少してしまった場合のリスクヘッジという意味合いも強いです」と語った。
こうして、次々と経営課題に取り組んでいる牧氏だが、今後については、「事業の拡大及び多角化を行う必要があると思っています。例えば、『浅草ときわ食堂』の人気商品の一つである“餃子”だけを提供する専門店を展開したり、比較的大規模な基幹店舗を作り、その周辺に小規模な店舗を展開するといった方法を考えていますが、まずは自分のペースでできる限り店舗を増やしていきたいですね」と語っている。