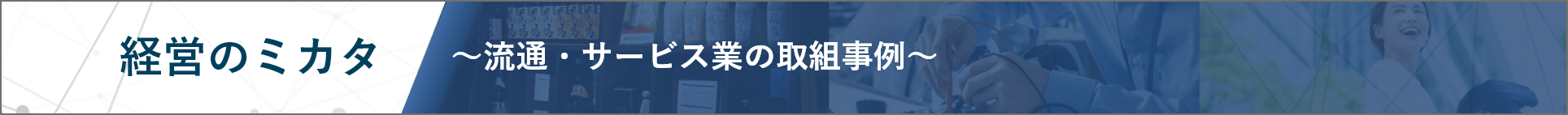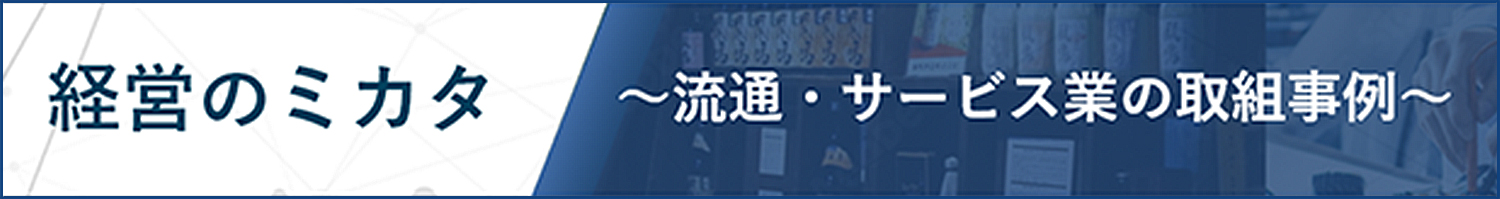2024年10月25日更新
玉川食品株式会社
| 所在地 | 東京都北区豊島7-5-12 |
|---|---|
| 代表者 | 関根 康弘(代表取締役) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 15人 |
| 設立年 | 1950年 |
| 企業HP | https://edo-tamagawaya.jp/ |

「江戸玉川屋」という文字の目立つ店舗
王子駅北口から徒歩約20分。江戸むらさき色のひさしに書かれたのは「江戸玉川屋」の文字。ここは東京23区に残る最後の乾麺メーカー、玉川食品の直売所だ。創業は1935年。2階は製麺工場、3階は麺の熟成乾燥庫となっており、現在は和洋中200種類以上の乾麺・生麺・蒸し麺を製造している。
“効率の対局にある麺づくり”をコンセプトに、手間暇を惜しまず、職人の技を活かした製法で知られる玉川食品。主力事業は1960年から関わってきた学校給食で、北区すべての小中学校をはじめ、城北にある6区175校の麺作りを受け持っている。それだけではなく、宮中祭祀である新嘗祭の奉納用うどんのほか、宮内庁の食堂や、シダックス・エームサービスなどの企業給食にも自家製麺を納めている。材料費が高騰し続ける昨今、3代目社長の関根康弘氏に同社事業の考え方について話を聞いた。
相次ぐ商品コラボにより認知度を向上

ハローキティーとコラボした「TOKYO PINK TONKOTSU RAMEN」
玉川食品の主力商品は、滑らかな喉越しが自慢の乾麺「満さくうどん」である。しかし、直近10年を振り返っても「満さくうどん」にのみ注力していれば良いというわけではなかった。
「2013年頃はまだまだ『満さくうどん』のネームバリューが低く、なかなかお客様に手に取ってもらえないという状態でした。そのため、最終的に『満さくうどん』にたどり着いてもらうことを目標として、お客様の興味を引くような新商品の開発に尽力してきたのです」と関根氏は語る。
まず手始めに開発に取り掛かったのが、焼成ウニ殻カルシウム麺(※)である。そこに目を付けたNATURAL LAWSONから声がかかり、コラボ商品としてプロテイン入りのうどんとパスタを製造することになった。 (※)ウニの殻を原料とした、玉川食品オリジナルのカルシウム強化麺
すると、他の企業からも次々と声がかかるように。2019年3月にサンリオのキャラクター・ハローキティとのコラボで麺もスープもピンク色の「TOKYO PINK TONKOTSU RAMEN」を発売すると、その麺を見たバンダイから問い合わせがあり、同年8月のガンダムカラーの5種類の麺の発売へとつながった。
次々とコラボ商品を展開することができた理由について、関根氏は「実際に麺を見ていただいた企業に、『満さくうどん』の質の高さを認識していただけたことが大きいです。技術面で信頼を得ることができたことに加えて、他企業との実績や製造面でのノウハウがあったことが多方面からお声がけをいただいた理由だと思います」と語る。
こうしたコラボのおかげでメディアへ取り上げられる回数も格段に増え、「江戸玉川屋」の認知度は高まっていった。
しかし、一方で漠然とした不安も抱えていたという。「学校給食という大きな事業の軸がある。ただ、もうひとつの柱としてコラボ商品をメインとしたお土産事業をこれ以上拡大していって良いのだろうか」。 そうした状況下で始まったのがコロナ禍である。
自社商品のファンを増やすために直売事業を強化

キッチンカーから店舗の顧客獲得につながることも
外出自粛の風潮の広がりによって玉川食品のお土産事業は大打撃を受けたという。その一方で、直売所で販売している多種多様な麺と、地元スーパーに卸していた乾麺が急激に売上を伸ばしていく状況を目にして、関根氏は気づかされたという。 「自社の商品を遠くの誰かに売ってもらうことを期待するのではなく、麺屋の基本に立ち返り、作った麺はやっぱり自分たちで売っていきたいと思いました。究極の理想は、会社の半径500m以内で事業が成り立つこと。そしてその円を広げていき、より多くの人々にファンになってもらうことです。コロナ禍を経て、地域に根づいた企業として成長していきたいと強く感じるようになりました」。
そこから玉川食品は、直接消費者とつながる直売事業をもうひとつの柱としていった。「自社商品のファンを増やすためには、多角的に商品を売り出すことが必要だと考えました」と関根氏は語る。そこで始めたのが、自社Webサイトでの販売強化や区内でのキッチンカー事業、自販機事業である。
現在、引き合いが特に多いのはキッチンカー事業だという。コロナ禍が落ち着き、区内各地でも野外イベントが増えてきた昨今、多い時は毎週キッチンカーを稼働している。「東京でうどんを提供しているキッチンカーは他の商品と比べると比較的数が少なく、オリジナリティをアピールできていると感じます。また、自社の商品をどのように調理すれば美味しく食べられるのか自分たちが一番良く知っているため、商品の魅力が伝わりやすく、召し上がったあとで乾麺の商品をその場で買ってくださるお客様も多いです。何より、キッチンカーを自社で所有していることによって、様々な企業から『うちのイベントで出店してください』といったお声がかかるようになったことが大きな収穫ですね」と、関根氏は手応えを感じている。

区内小学生の工場見学の様子
さらに、同社は自社商品のファンを増やす取組として、工場見学や職場体験などの受入も積極的に進めている。そんな中で、長年工場見学を受け入れている北区の小学校の児童から受けた質問をきっかけに「食品リサイクル」の試みも始めたという。
「麺を乾かす時は竹竿に吊るして折り返すので、竹竿にかけた部分と下の部分は曲がってしまい商品化できないため、廃棄することになります。これを工場見学で訪れた小学生に説明した際、ある児童から『もったいない』という声が上がりました。そこで、厚木にある養豚場と交渉し、廃棄せざるを得ない麺を飼料として買っていただく代わりに、厚木市産のブランド豚である『あつぎ豚』を購入してキッチンカーで使用することにしました」と関根氏。 現在このフードロス対策の取り組みは北区の学校教材で紹介されているほか、曲がった麺の節麺(ふしめん)は北区内の学校給食において「節麺汁」として活用されている。
麺製作に特化し、既存顧客へのアプローチを見直す
一方、コロナ前まで玉川食品の主軸となっていたお土産事業にも大きな変化があった。 「お土産事業で企業とコラボする際、以前はスープやかやくの調達、パッケージの管理にも関わっていましたが、現在は麺製作のみ手がけています」と関根氏は打ち明ける。数々の大企業とのコラボを経て、コロナ禍のように何かあった際のリスクを考えると、あれこれと手を出すよりも中小企業の規模感に合わせて一つのことに集中する方が、継続性が高く成功しやすいことを実感したという。
さらに最近、関根氏は中小企業診断士との相談の中で大きな気づきを得た。 「玉川食品の事業は典型的な“八二の法則”で、上位20社への売上が約8割を占めています。売上を整理し、その20社への販売状況を一覧表で見ていた際、診断士の方に『チルド麺のみ購入されている企業に対して、乾麺もしっかりと売り込んでいますか?』と聞かれたのです。というのも、チルド麺と乾麺の両方を購入してくださっているのは1社のみ。しかし、玉川食品の強みは乾麺もチルド麺も製作できるところです。確かに既存の取引先に両方の麺を販売することができれば、効率的に売上げアップを目指せます」。 関根氏は、既存顧客の大切さを改めて実感しているという。
「現在は足元のお客様へのアプローチに注力しているところです。既存顧客と地元・北区での評価を高めつつ、23区内唯一の乾麺製造という強みを活かして、いずれは東京都内の他エリアの学校給食にも乾麺を売り込んでいきたいですね」。関根氏は最後にそう語った。