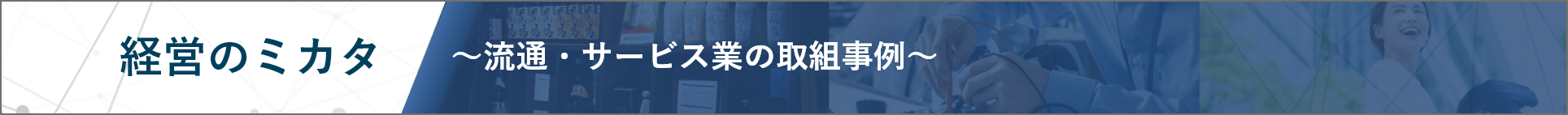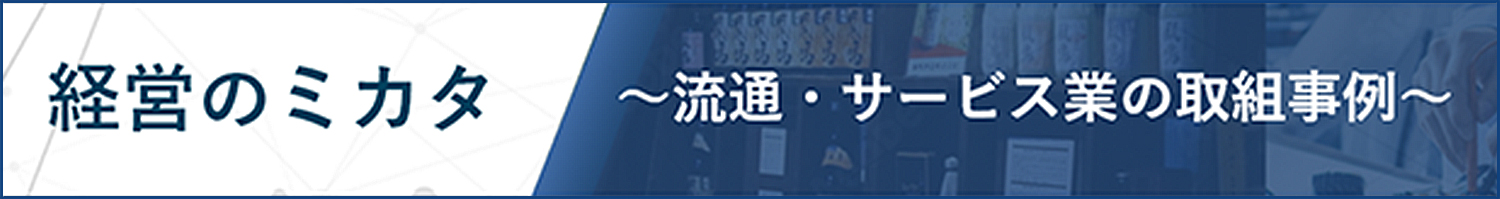2024年10月15日更新
株式会社東京繁田園茶舗
| 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷南1-14-16 |
|---|---|
| 代表者 | 繁田 穣(代表取締役) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 20人 |
| 設立年 | 1947年 |
| 企業HP | https://handaen.official.ec/ |
丸ノ内線・南阿佐ケ谷駅から徒歩約3分、買い物客で賑わう商店街の一角に本店を構えるのが日本茶専門店「東京繁田園茶舗」だ。1815年より茶業を営んでいた「繁田園」の東京支店として、1947年にこの阿佐ヶ谷の地で誕生した同社。実に70年以上もの間、全国から仕入れた高品質なお茶を顧客へ届け続けている。
しかし、その道のりは決して平坦とは言えない。内需の低下や後継者不足などによって日本茶業界全体が苦境にあえぐ中、東京繁田園茶舗も一時は廃業するか否かの瀬戸際にあった。一時は関東に7箇所あった店舗も順次閉店し、現在は阿佐ヶ谷本店と荻窪店の2店舗を数えるのみだ。そんな中、2021年に家業を継いだ3代目・繁田穣氏は、いとこで大手出版社出身の株式会社Nodes・藤田真理子氏と連携し、経営を再生。フランス・パリで行われた大型展示会「JAPAN EXPO PARIS 2024」などへの出展を通じて、日本茶文化の海外への普及にも挑戦している。
10年で売上が半減。苦境に立たされる中、ECやイベントで新たな「見せ方」を打ち出す

デザインリニューアル第1号の「長谷部さん家のさわやか紅茶」
「もう、店をやめようと思う」。繁田穣氏の父である豊氏がそう親族の前で口にしたのは、2020頃のことだ。
しかし、「このまま終わるのはもったいない」と大手百貨店を退職して家業を継いだ繁田氏は、大手出版社にて海外営業や書籍編集を経験し、独立・起業していたいとこの藤田氏と手を組んだ。ちなみに、藤田氏も旧姓は繁田であり、繁田穣氏とは同じ阿佐ヶ谷本店の3Fと4Fで生まれ育った仲である。
日本茶市場を取り巻く環境は非常に厳しい。「1980年代にペットボトル入りの緑茶が登場してからというもの、急須で淹れるお茶の市場は30年で40%近くに縮小。都内の日本茶専門店の数も1/10に減少し、東京繁田園茶舗の売上も10年で半減しました」と藤田氏は説明する。 一方、生産者を悩ませているのは、急須で淹れるお茶の需要縮小に伴う「一番茶」の価格下落だ「いいものを作ってもお金にならない」という苦しい状況に、生産者の高齢化や後継者不足、物流コストの増大や肥料の値上げといった課題が拍車をかけていた。
大きな課題に直面している市場において、いかにして経営を再生するか。2人が採ったのは、事業を整理して「守り」を固めつつ、一定の予算を新規施策に充て、既存事業とのバランスを取りながらも積極的に「攻め」ていく姿勢だった。
「まずは、採算の厳しい店舗の閉店や倉庫の返却などを行い、経営のスリム化を行いました。
残すことに決めた阿佐ヶ谷本店と荻窪店の運営についても、やるべきことは山ほどありました。しかし、先代社長や何十年にも渡って当店に勤務してきたスタッフもいる中で、3代目になったばかりの私が急進的に改革を進めては、摩擦が起きかねません。まずは自ら業務に入り、スタッフと一緒に、時間をかけて改善を進める必要がありました。
そこで、並行して注力したのがオンライン周りの施策です。オンラインショップを開設し、新たに日本茶の定期便サービスを開始、藤田にはX(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSアカウントを立ち上げてもらいました。オンラインの施策であれば、店舗の運営とは切り離し、スピード感を持って取り組むことができますから」と繁田氏。
オンラインショップやSNSの運用を経て、次に藤田氏が提案したのは、商品パッケージのリニューアルだった。試飲や口頭での説明ができないオンラインショップでは、ビジュアルのインパクトでユーザーを惹きつけつつ、商品購入後の体験を保証するような丁寧な説明が必要だと考えたからだ。
「日本茶の敷居を高くしている理由のひとつが、『淹れ方がわからない』というものです。煎茶をはじめとする日本茶は、お湯の温度や量によって味が大きく変わってしまうのですが、これまでは店頭で説明ができていたため、パッケージには具体的な説明の記載がありませんでした。しかし、オンラインショップのお客様には口頭で説明をすることはできません。パッケージを見ただけで、それぞれのお茶に適切な茶葉の量やお湯の量、温度、抽出時間がわかるようにしたいと思いました」と藤田氏は語る。

「見せ方」を意識したデザイン
「しかし、既存商品のパッケージを全面的にリニューアルするには、大きなコストやリスクがかかる。そこで、まずは定期便の1アイテムだったみかん入り和紅茶「長谷部さん家のさわやか紅茶」のデザインから始めた。当時20代のデザイナーによる親しみやすいパッケージデザインは、幅広い世代の共感を呼び、SNS上にはパッケージ写真付きの投稿が溢れた。
しかし、意外な効果は社内に起きた。何十年も同店に勤務してきたスタッフたちが、 「パッケージが素敵」と自ら進んで商品を購入したのだ。たしかな手応えを感じた藤田氏は、その後も次々と、新たな感性で新商品の企画を進めていった。
また、嗜好の多様化に合わせて、容量のラインナップも拡充した。従来、100g入りのみの展開だった商品に新たに30g入りのシリーズを発売し、ティーバッグも5個入りと24個入りの2サイズを展開した。 「従来は、決まった1種類のお茶を購入され続けるお客様が多かったのですが、近年は『いろんな味を試したい』『ちょっとしたギフトとしてお茶を送りたい』といったニーズも増えてきているように思います。品質には自信があるからこそ、商品そのものには手を加えず、『見せ方』を変えることで、多様なニーズに応えたいと考えています。」と繁田氏は語る。
藤田氏が新たな施策を積極的に進め、繁田氏が既存業務の改善に取り組む。こうした役割分担をしながら、オンラインと店頭での販売を徐々に連動させ、東京繁田園茶舗は生まれ変わってきた。
しかし同時に「国内の市場が縮小していくスピードに、盛り返すスピードが追いつかないという感覚がありました」と藤田氏は述べる。
ポップアップ出店をきっかけに海外需要を強く意識

盛況となった「JAPAN EXPO PARIS 2024」
東京繁田園茶舗が海外需要を強く意識したきっかけは、2023年4月に行った吉祥寺マルイへのポップアップ出店だ。 パッケージデザインを新しくしたものの、そもそも入店する敷居が高いのではないかと考え、全く異なる場所でテストマーケティングしてみようと1週間ほどの出店を決めた。 すると、購買層の1~2割が海外からの訪日客だった。とりわけ驚いたのは、その購買力の力強さだ。 「日本人のお客様もいらっしゃいましたが、商品への関心度合いや購買単価が明らかに違いました。日本茶の輸出が右肩上がりになっていたこともあり、『いよいよ本格的に海外に注力していくべきなのではないか』と考え始めました」と藤田氏は振り返る。
前年の2022年8月から、経済産業省の国際化促進インターンシップ事業を活用して外国人インターン生2名を受け入れ、市場調査や戦略立案を行って海外展開可能性を模索していた藤田氏。
そんな折、こう毎年7月にパリで開催される世界最大級のジャパンフェスティバル「JAPAN EXPO PARIS 2024」へ出展しないかと打診を受け、思い切って出展を決めた。実は繁田園には、1900年開催のパリ万博に日本茶を出品して大賞牌(グランプリ)を獲得したという歴史もあり、遠い先祖のパリへの挑戦を124年ぶりに引き継ぐという意味でも面白いと考えたのだ。
しかし、経営再建の真っ只中にあった同社にとって、海外の展示会出展にかかる費用は小さなものではなかった。そこで藤田氏が提案したのが、クラウドファンディングの活用だった。
繁田氏は、「もちろん、当初の目的は資金面での支援を得ることです。しかし、私たちにとってより大きな意味があったのは、今回のクラウドファンディングを通じて、『東京繁田園茶舗とはどういう店なのか』を多くの人に知ってもらえたことでした。地元の方々からも、『こんなに歴史のあるお店だったなんて知らなかった!』といったお声を多くいただき、インパクトの大きさを実感しました」と強調する。
「日本茶の美味しさを、世界に伝えたい」。そんなメッセージのもと始まったクラウドファンディングは、目標金額の175%を達成。当初の予定よりブースを拡大して臨んだ「JAPAN EXPO PARIS 2024」では、日本茶の試飲・販売や茶道のワークショップなどを実施し、大成功を収めた。
「ブースでお買い物をしてくださったお客様は4日間で約500名。円安の影響もあり、売上は約100万円にのぼりました。多くの発見があり、市場調査としても大きな収穫がありました」と藤田氏。たとえば、ブースを訪れた参加者の中には茶筅(ちゃせん:お抹茶を点てる際に使用する茶道具)を持っている人も非常に多く、市場のポテンシャルを実感したという。「この出展をきっかけに、パリの日本食料品店や飲食店とのつながりが生まれたり、2024年12月にバルセロナで開催される日本文化の祭典『Manga Barcelona』出展へのお声がけをいただいたりと、新たな展開も生まれています」と語る。
店頭での接客に直接繋がらない業務の自動化・DX化を進める

東京繁田園茶舗阿佐ヶ谷本店の趣ある店内
「日本茶文化を次の世代に引き継いでいく。その方向から外れない限り、様々なことにチャレンジしたい」と話す繁田氏は、外部に対する「見せ方」を洗練させるだけでなく、ひとつひとつの業務改革にも取り組んでいる。「まずは旧来型のレジをPOSレジアプリ『Airレジ』に変更し、手書き集計等のアナログな作業が発生しない体制を整えました。他にも、会計ソフトと銀行口座を自動で連携するように切り替える、FAXではなくメールで受注作業を行う、スプレッドシートで在庫を管理するなど、効率化を図りました」と語った。
そして、こうした自動化・DX化の大きな目的は、顧客の体験価値向上に繋がらない業務をとことん減らし、顧客への対応に注力してもらうことにあるという。「以前は、こうした事務作業を店頭でこなしていました。しかし店頭は接客をする場所、お客様へ『体験』を提供するところです。従業員には、お客様の滞留時間や来店回数を伸ばすために、店頭を盛り上げてほしい。そのために、お客様の体験価値向上に直接繋がらない業務は、極力削減していきたいです」と繁田氏は語る。
現在は、商品のPRに関してもインターネットやSNSを活用できている。「商品や生産者の情報、おすすめの淹れ方について、オンラインショップの商品ページや各種SNSで発信しています。事前にネットで情報を調べ、購入したい商品を決めて来店されるお客様も増えている印象ですね。オンラインでの取り組みと、業務効率化が功を奏し、近年は店頭の売上も伸び続けています」と繁田氏。市場に変化を生み出し、日本茶文化を次の世代に伝えていくために、東京繁田園茶舗の挑戦は続いていく。