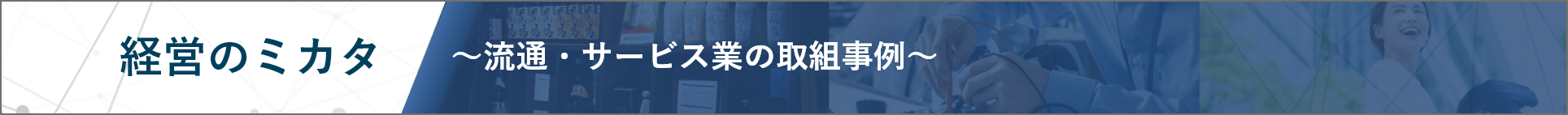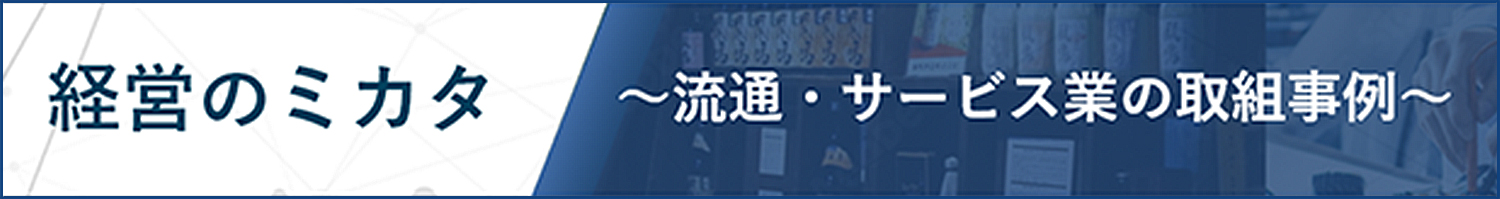2024年11月15日更新
株式会社江戸切子の店 華硝
| 所在地 | 東京都江東区亀戸3-49-21 |
|---|---|
| 代表者 | 熊倉 節子(代表取締役社長) |
| 資本金 | 500万円 |
| 従業員数 | 12人 |
| 設立年 | 1992年 |
| 企業HP | https://www.edokiriko.co.jp/ |
繊細なガラス細工で知られる東京の伝統工芸品・江戸切子。その発祥の地とされる日本橋の一角に店舗を構えるのが、「江戸切子の店 華硝」だ。全て手作業で製造される華硝の江戸切子は国内外から高い評価を受けており、2008年に開催された北海道洞爺湖サミットや、2023年の日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議で国賓に贈呈されている。さらに、2024年4月には2代目・熊倉隆一氏が春の叙勲(じょくん:国が勲章を授与すること)で「旭日単光章(きょくじつたんこうしょう)」を受章するなど、ますます存在感を増している。
華硝を支えているのは、確かな技術力や芸術的センスだけではない。代表取締役である熊倉千砂都氏が進める発信の強化や、一般向け江戸切子スクールの開校、海外需要を見据えた施策といった数々の取り組みが、売上や事業の継続性、採用力の向上に繋がっている。
メルマガや老舗とのコラボ商品、工房ツアーなどのPR活動に注力

江戸切子のデザインを取り入れた江戸扇子
(コラボ商品)
華硝は1946年、江東区亀戸にて千砂都氏の祖父が工房として創業。当初は大手ガラスメーカーの下請けとして加工を請け負っていた。しかし、父の隆一さんが2代目職人となってからは「同じものばかり作っていると技術の向上を見込めない」「お客様により良い商品を届けたい」といった気持ちから製造小売へと業態転換。千砂都氏は、「当時は『百貨店に置いてある商品は質が良く、そうでないものは質が悪い』と判断する風潮がありました。そんな中、華硝は卸販売をせずに直営でやっていくと決めていたため、集客に大変苦労したようです」と振り返る。何百万円もかけて新聞広告を出稿したにもかかわらず、来客が全くなかったこともあったという。
そうした経験もあり、千砂都氏が取締役となってからは、情報発信に力を入れた。InstagramやFacebook、ブログなど様々な媒体を試してみたところ、特に顧客からの反応が大きかったのはメルマガだった。「1~2か月に1回、新商品やイベントの情報を掲載したメルマガを発信しています。現在の登録者数は約900名。メルマガを見たお客様から『よかったら画像を送ってもらえませんか』などとダイレクトにメールをいただき、商談につながることもあります」と千砂都氏。
さらに、PR媒体の特性に応じて発信内容も工夫しているという。 「メルマガは各号ごとにイベントの集客などの明確な目的をもって配信している一方、簡単に発信・閲覧ができるInstagramについては、気軽に商品を見てもらう場として位置付け、それぞれのスタッフが手の空いた時間で江戸切子の写真を投稿しています」と語った。
また、SNSやメルマガ以外のPR活動にも積極的だ。そのひとつが、2016年の日本橋店のオープン後に進められた老舗店とのコラボである。顧客を通じて知り合った日本橋周辺の店との共同開発で、手ぬぐいや扇子、風呂敷、浴衣など、江戸切子のデザインを盛り込んだ商品を次々に送り出した。結果、「江戸切子のグラスは高くて手が届かないけれど、1,000円の手ぬぐいなら買える」といった新規顧客層を開拓できている。 また、亀戸本店で試験的に開催している工房ツアーも好評だ。従来はメディアにのみ立ち入りを許可していた工房で、一般客も江戸切子の製造工程を見学・体験することができる。「2代目職人である父の製作を傍で見学され、言葉を交わす。その後、日本橋店にお越しになり『2代目の作品を買いたい』と購入して帰られる方も多く、大変嬉しく感じています」と千砂都氏は笑顔を見せる。
江戸切子スクールの運営で安定した収益&即戦力人材を確保
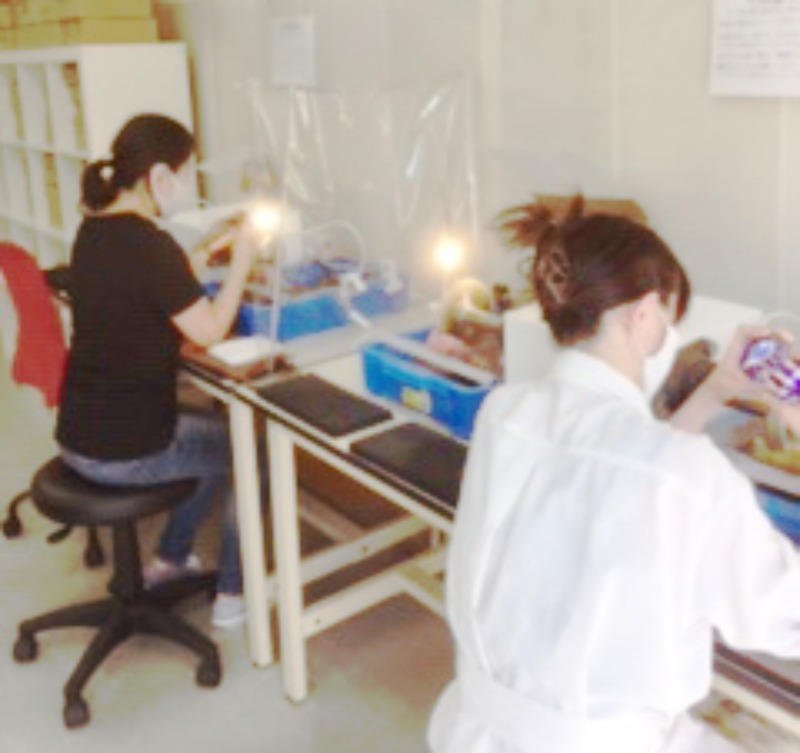
江戸切子スクール「HANASHYO'S」の様子
華硝では、2011年より江戸切子職人が経営する国内唯一の江戸切子スクール「HANASHYO'S」を運営していることも特徴的な取り組みだ。体験、入門、初級、中級、上級、インストラクター、江戸切子職人養成の7つのコースに分かれており、レベルに応じて受講可能となっている。「『江戸切子を作る場所があったら嬉しい』というお客様の声にお応えして始めた取り組みです。開校当初の受講者数は4~5名ほどでしたが、現在は約200名。1~2週間に1回程度通う方が多く、30~40代の女性がメインです」と千砂都氏は説明する。
江戸切子スクールのもたらした恩恵は、主に2つある。ひとつは毎月安定した収入を見込めるため、店舗の売上が多少落ち込んでも焦らなくて済むという点。そして、もうひとつは人材育成のしやすさだ。「大学などで江戸切子の技術を習得した人材を採用しようとすると、華硝のやり方に馴染ませるために一度ついた型を外してもらわなければなりません。でも、江戸切子スクールの出身者ならそういった必要がなく、技術承継がしやすいのです」と千砂都氏は強調する。また、接客スタッフに関しても、繊細な江戸切子を扱うことからガラスに慣れている人材のほうが望ましい。そのため、華硝では職人含めスタッフの約7割をスクール出身者から採用しているという。
事業の継続性の向上という意味では、別の施策も行っている。2代目職人の隆一氏および10年以上経験を積んだ高弟(※)2名の計3名でチームを組み、ブランド「華組」として製作に臨んでいるのだ。千砂都氏は「華硝に代々伝わる江戸切子の技術は、3代目職人である弟の隆行がしっかりと受け継いでいます。しかし、弟のみが技術を承継する形では、何かあった場合に華硝の伝統が途絶えてしまう。そこで、次世代へしっかりと技術を継承できるようシステム化しています」と語る。 (※)弟子の中でも特に優れた者のこと
このようにスクールや技術承継の体制がしっかりと確立されている一方で、華硝では女性職人や販売スタッフの離職率の高さという課題に直面しているという。この課題解決に向けて、ある程度熟練した職人なら比較的手軽に作れる商品に関しては、ゆくゆくは分業制の工房を設け、そこで育児中の女性などがパートで働けるような体制をつくりたいと考えている。また、千砂都氏は「外部の人事コンサルタントに委託し、採用力の向上や離職率低下を目指しているところです。外部の目があるというのは大きいですね」と話す。
インバウンド客が1割から3~4割に増加。海外市場の開拓を狙う

華硝を代表する最高技術「米つなぎ」を盛り込んだ
ワイングラス
千砂都氏は、「日本のみでは市場に限りがある」と実感している。実際、以前は1割程度だったインバウンドの顧客が近年は3~4割に増加。華硝の江戸切子を使用しているホテルや日本料理店からの紹介のほか、Googleの口コミをきっかけに来店する外国人客も多いという。「特にアメリカや中国のお客様からご好評いただいています。お金に糸目をつけず、ご自宅用やお土産用として10セットほど買っていかれる方もいらっしゃいますよ」と千砂都氏は微笑む。
インバウンド客が増えるに従い、売れる商品の割合も変わってきた。かつての内訳は一点物の商品が3割、レギュラー商品が7割ほどだったが、現在はその割合が逆転し、一点物7割、レギュラー商品3割となっている。 「需要の変化に合わせて製造する商品の割合も変更しました。一点物を多く置くようになったことで、お客様の総数が多少減った半面、客単価が高くなったため、全体の売上は増加しています。また、お客様の数が減ったことにより、一人ひとりに対する接客をより丁寧に行うことができるようになったという利点もあります」と千砂都氏は語る。
海外市場をさらに開拓するため、千砂都氏は様々な施策を進めている。そのひとつが、海外向けホームページやメルマガの制作だ。日本向けのサイトは情報量が多ければ多いほど喜ばれる傾向にあるが、海外の消費者が閲覧するサイトでは大きな画像や映像を取り入れるほうが訴求力は高いと言われている。「江戸切子を単なるガラス食器ととらえられてしまうと、『食器にしては値段が張る』と受け取られかねません。そこで、江戸切子の唯一無二の魅力が直感的にわかるような画像や映像を多く盛り込んでいるほか、江戸切子のアート性をアピールできるようオランダ在住の日本人コンサルタントに協力を仰ぎ、海外向けホームページ用の文章を書いていただいています」と千砂都氏は述べる。
また、海外にショールームを設け、そこでネットを通じて日本の店舗を見てもらうことも考えている。そのために、千砂都氏は語学のみならずデジタルマーケティングやeコマースを学んでいる最中だという。
さらに、展示会への出展にも意欲的だ。「以前も東京都のプロジェクトの一環で海外の展示会に出展していたのですが、その後商談に繋げるまでの対応を仕組み化していなかったため、展示会に出ただけで終わってしまっていました」と千砂都氏は悔しさを滲ませる。今後は卸先をどこにするか、個人が展示会で購入する際のフローはどうするかなど、しっかりと体制を整えたうえで出展したいそうだ。
「今後は国内のみならず、海外のファンも増やせたら嬉しいです。そのために必要なシステムや販促方法をきちんと構築し、華硝の江戸切子をワールドワイドに広めていきたいと考えています」千砂都氏は、最後にそう締めくくった。