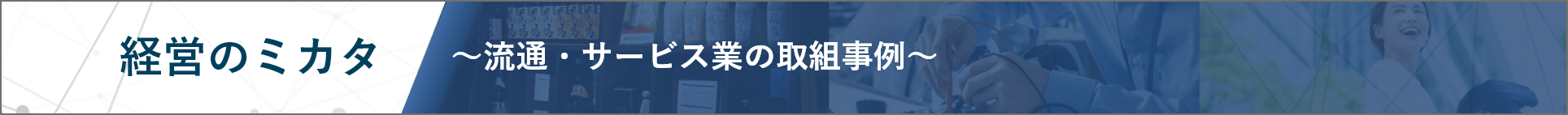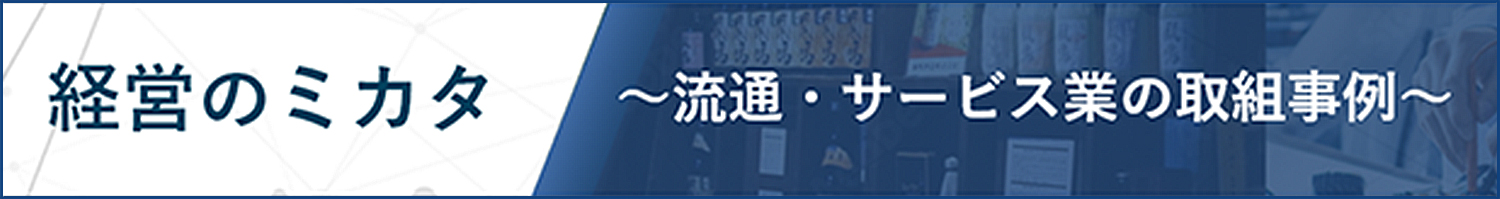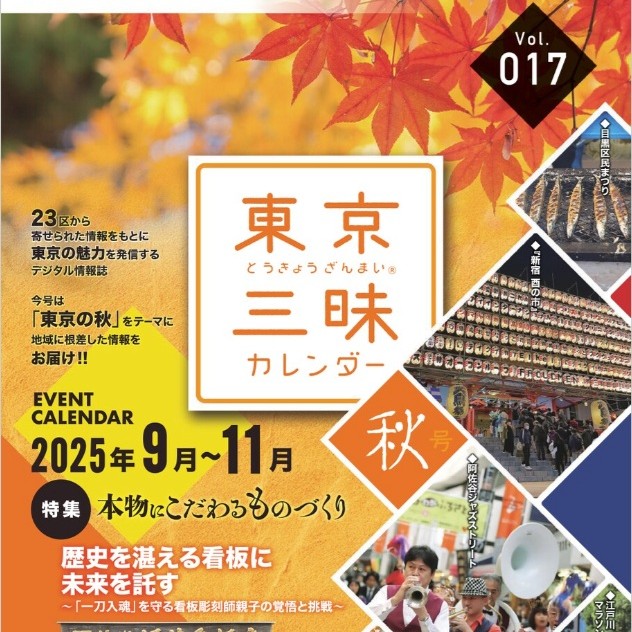2025年2月12日更新
有限会社小池精米店
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-14-17 |
|---|---|
| 代表者 | 小池 理雄(代表取締役三代目) |
| 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | 2人 |
| 設立年 | 1978年 |
| 企業HP | https://komeya.biz/ |
JR原宿駅から徒歩約7分。キャットストリートのほど近くに店舗を構える小池精米店は、原宿の地で1930年から続く米屋だ。2006年に代表取締役三代目に就任した小池理雄氏は、47都道府県のお米をモチーフにしたロゴマークを作成したり、お米に関するイベントを手掛けたりと、精力的に「お米の楽しさ」を伝えている。地域の人口減少という逆風の中、右肩上がりの成長が止まらない小池精米店。その地盤となっているのは、確かなブランディングと、小池氏の強い発信力が生んだ多くのファンたちだ。
小池精米店のロゴマークを作成し、企業理念を可視化
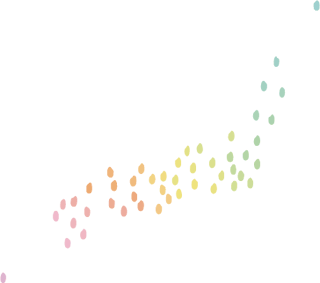
小池精米店を象徴するロゴマーク

子供向けのイベントも精力的に開催
二代目である父が倒れたことをきっかけに、家業を継いだ小池氏。それまで企業に勤めていた小池氏は、ほかの米屋に比べるとまさに“新米”だった。小池氏は「まずはお米のことを深く知りたい」と勉強に励み、全国でも数少ない「五ツ星お米マイスター」の資格を取得。そして、新規開拓のための営業活動に明け暮れるさなか、東日本大震災が起きた。
「震災をきっかけにお米の買い占めが起きました。需要はあるのに在庫がないため、お米を販売することができず時間を持て余していました。そんな日々を過ごしていた時、原点に立ち返り、なぜ原宿という地でわざわざ精米店を経営しているのか、その意義づけを明確にしたいと思ったのです。会社としての方針がブレないようにするためにも『小池精米店の存在意義を一言で説明できるツールが欲しい』と考えるようになり、小池精米店を象徴するロゴマークを作ることにしました」と小池氏は振り返る。
試行錯誤の上、各都道府県のお米の形状を一つ一つ抜き出し、日本地図を形作ったロゴマークが完成した。「『全国四十七都道府県のお米と食卓をつなげたい。』という当店の理念をうまく可視化できたと感じています。また、理念を見つめなおすことで、会社としての方針もよりしっかりと固まりました」と小池氏は話す。
さらに、東北復興の願いを込め、東北6県のお米「あきたこまち」「ササニシキ」「ひとめぼれ」「まっしぐら」「つや姫」「コシヒカリ」を詰め合わせたギフト用新商品「あ・さ・ひ・ま・つ・光」を開発。名前の由来はそれぞれのお米から言葉を「一粒」ずつ抜き出して名付けたことだという。 その他にも米の食べ比べイベントを主催したり、ECサイトを制作したりと「お米の楽しさ」を様々な角度から伝える試みを行った。ECサイトにおいては小池氏の実食レビューや生産者の顔写真、顧客からの感想を掲載し、好評を博している。「お米の味の違いは、一般消費者にとってどうしても分かりにくい。そのため、『生産者の熱意』や『環境への配慮』などの味以外のポイントにも焦点を当てることで付加価値を創出し、他店と差別化できないかと工夫しました」と小池氏は語る。
小池氏の革新的な取り組みは自然と話題を集め、メディアへの紹介や連載、コンサル、講演の依頼が続々と舞い込むようになる。こうした発信力やブランディングの根底にあるのは、「小池精米店のファンになってもらいたい」という強い想いだ。これを原動力に多角的な活動を続ける小池氏の戦略が功を奏し、着実にファンを増やしている。
SNSやイベント活動などを通じ、客単価の高い取引先を開拓

取材当日もお米のTシャツを着用していた小池氏
戦前から戦後にかけて“地域の米屋”として愛されてきた小池精米店も、近隣住民の減少にともない、現在は売上の約8割が卸売となっている。メインの取引先は、高級寿司店といった比較的客単価の高い飲食店だ。注文があれば、銀座や日本橋などにも配達に向かう。「SNSやお米に関するイベント活動、会合を通じて、寿司店を中心に知り合った取引先が多いですね。寿司店は横の繋がりが強いため、一人の大将が気に入ってくださると一気に界隈へ広まるのです。特に、“五ツ星お米マイスター”を取得する中で身に着けたお米のブレンド技術を活かした、お寿司に合うブレンド米の美味しさを高く評価していただけていますね」と小池氏は破顔する。
初めて寿司店にアプローチをしたのは、知人の業者を介してだった。その業者との繋がりを持ったのも、小池氏主催の米関連イベントがきっかけだったという。米の楽しさを広めるため、そして自店の存在をPRするために、「お米ごとにどのおかずが合うか」「おにぎりを作りやすい品種は何か」といったテーマのイベントを意欲的に開催してきた小池氏の努力が、人脈形成にも大いに役立ったのだ。
コロナ禍になると売上こそ落ち込んだものの、取引先数は着実に増加。「飲食店では、お客様の足が遠のく中でメニューの見直しを行ったのだと思います。結果、『お米の良し悪しで他店との差別化ができるのではないか』といった考えに至り、お米にもこだわりを持つお店が増えたのではないでしょうか」と小池氏は推測する。
そして、コロナ禍が収束するとともに、飲食店からの需要は復活。新しい取引先も加速度的に増え、小池氏は全国の米農家の元を飛び回りながら多忙な日々を送っている。「最近も、『自分の店を持ちたいので勉強させてほしい』という若者や、『ネットで小池精米店のことを知り、興味を持った』という岡山の鰻専門店などからご連絡をいただきました。お問い合わせを下さった方は、そのまま顧客になるケースがほとんどです。SNSなどを通じて小池精米店についてご存知の方が多く、期待するイメージとの齟齬が生じにくいのだと思います」と小池氏は述べる。
米の高騰による取引先の減少も、小売先拡大へのチャンスととらえる

農家の方とのつながりも大切にしている
新規開拓が進む一方で、2024年夏の「令和の米騒動」とも呼ばれる米不足による影響は免れなかった。「今も四苦八苦しています」と小池氏が言うように、米の生産量が需要に追いついていないため、産地に在庫がなく、仕入れ値が高騰していることから、卸先にも値上げせざるを得ない。価格改定に難色を示す飲食店も少なくなく、やむを得ず主要な取引先から手を引いたこともあるという。実際、米の売価としては20年前と同程度の価格に戻っただけなのだが、長らく安い価格に慣れていた取引先がこの状況に適応するまでには時間がかかると小池氏はみている。
しかし、小池氏はそれすらチャンスだととらえている。「大規模飲食店向けの卸売は薄利多売のため、利幅自体は小さいのです。そのため、小規模でも、弊社と取引したいと言ってくださるところと関係を結んでいきたいですね。その代わり、これを機に利幅の大きい家庭向けの小売を強化したいと考えています。ECサイトも今は忙しくてそこまで手が回っていないですが、有意義なツールなので、もっと内容を充実させていきたいですね」と語る。
「弊社は超零細企業だからこそ、いかにファンをつけるかが重要です。『小池精米店のお米』に感情移入し、購入していただけるようSNSなどで発信を続けています」。そう改めて強調する小池氏は、お米の魅力を高い熱量で消費者に届けるべく、自らの足で熱心に全国各地の米農家を訪問し、農家との関係性構築に努めている。「産地のことを詳しく知りたいという目的ももちろんありますが、何より直接足を運ぶと生産者の方に喜んでいただけるのが嬉しいですね。これからも、既存の農家さんとのご縁を大切にしながら商品開発などに取り組んでいきたいと考えています」と小池氏は言う。
「今後は、もっとイベントを充実させたいですね。たとえば『産地と消費地を、お米を介して結ぶ』という理念に合わせ、農家と一般消費者が一堂に会する『農家サミット』や、インバウンド向けにお米の知識を教えるイベント・食育指導など、面白いことにたくさんチャレンジしていきたいです」と小池氏は展望を語る。
人も街も移り変わりの激しい原宿の一角で、老舗米屋の挑戦は続いていく。