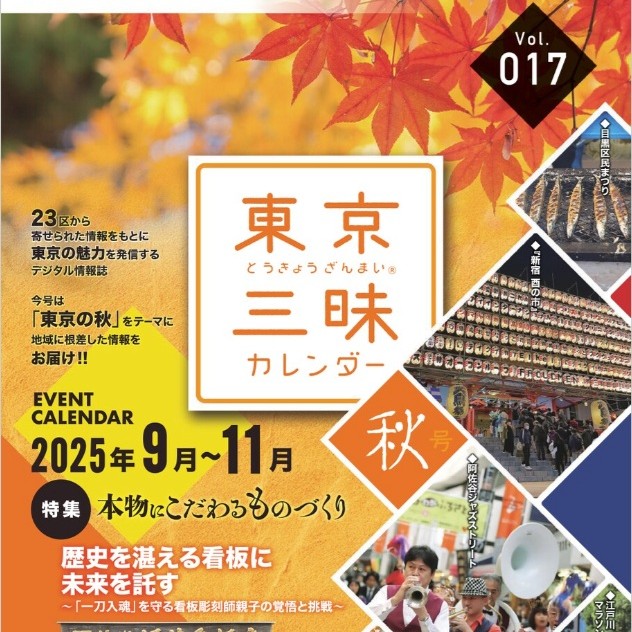2025年8月7日更新
株式会社大治
| 所在地 | 東京都大田区東海3-2-6 |
|---|---|
| 代表者 | 本多 諭 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員数 | 130人 |
| 設立年 | 1949年 |
| 企業HP | https://daiharu.co.jp/wp-daiharu/ |
青果部門で日本一の規模を誇る、東京都中央卸売市場の大田市場。昼夜を通して賑わう市場の中に店舗を構えるのが、青果物の仲卸業を営む株式会社大治だ。仲卸とは、市場のせりなどで品物を買い付け、小売店や飲食店へ販売する中間業者を指す。
同社は、70年以上培ってきた目利き力や、仲卸としては珍しい独自の物流網を活かした高品質・高価格商品の供給を実現している。また、いち早く有機野菜や東京野菜®(※1)の販売・ブランディングに注力しているほか、法人向けの農園体験プログラム「千菜一遇 農en」を提供するなど、その取り組みは目ざましい。農家や地域とも密に連携しながら、同社はさらなる成長を目指している。
※1「東京野菜®」は(株)大治の登録商標。
鮮度管理やプロの「目利き力」、青果物のブランド化を通じて高品質・高価格商品を提供

独自の自社物流網を持つ

東京野菜®のブランドロゴ
大治の主な顧客は、「成城石井」「紀ノ国屋」といった高級スーパーや飲食店だ。大田市場の前身である神田市場で軒を並べていた紀ノ国屋へ卸したことが、高級スーパーをメインの取引先とするようになったきっかけだという。「そこから、当社のブランドイメージが確立されたと思います」と、大治営業部 新規業務開発担当の山口大樹氏は話す。
現在の売上構成比は概ね小売店6割、飲食店4割。ブランドイメージにふさわしい高品質・高価格商品を提供するための施策の一つが、自社物流網による直接納品だ。「配送先は一日約700箇所。朝だけでも40便ほど稼働しています。直接納品により高い鮮度を維持した上、プロの目で品定めした状態でお届けできることが当社の強みです」と山口氏は言う。
以前から、ピッキングやスーパー向けの小分け作業は大田市場北口にある低温物流センターで行っていた。加えて、2025年4月、新たに八潮センターを増設。「八潮センターでは、人気上位100品目について専門の担当者が品定めを行い、最終選別を経たものが保管されています。この体制により、従来以上に品質管理が徹底されるようになりました」と山口氏は語る。
さらに、高品質の商品を提供するため、市場取引のみならず独自の流通ルートを使用した産地直送にも力を入れている。その一環として、市場ではあまり取り扱われない有機野菜や東京野菜をブランド化し、提供しているという。山口氏によれば、「有機しいたけであっても、市場では単に『しいたけ』として取引されるのが一般的」だ。だが、有機JASマークや生産者情報を表示することで、顧客への訴求力が向上するだけではなく、市場流通品に比べて自由に価格を設定できるというメリットがある。「近年、地場野菜の人気が高まっていますが、はじめに『東京野菜』というブランドで売り出したのは当社だと思います」
このように付加価値を創出することと並行して、大治は物流コストを抑える取り組みにも注力している。「早朝に出発するトラックは、納品を終えた後、そのまま近くの産地で野菜を集荷します。空車での走行を削減しているわけです」と、山口氏は効率的な物流体制について言及する。
企業向けの農業体験プログラムや、農産物の事前予約受け取りサービスを開始

「千菜一遇 農en」の様子
近年こそSDGsや地産地消への関心が高まっているが、約30年前に東京野菜を売り出した頃は、なかなかその価値を伝えることができなかったという。さらに、コロナ禍で卸先である飲食業界が大打撃を受け、売上が激減した。
「東京野菜をブランディングしつつ、新たな販路を開拓したい」。その課題をクリアするために生み出した新規事業が、法人向けの農業体験プログラム「千菜一遇 農en」だ。これは企業に2アール(200㎡)の農地を貸し出し、農家のサポートを受けながら農業体験をしてもらうというもの。企業は収穫した農産物でオリジナルノベルティを製作したり、SDGs活動の一環で籾殻(※2)由来の「バイオ炭」を畑に撒いて野菜を育て、温室効果ガス削減に取り組んだりと、活用目的は様々だ。
「福利厚生はもちろん、CSR活動(※2)の一環として利用される企業様も多いですね。リピート率も高いです」と山口氏は話す。運営においては、農家側にもしっかりとした経済的メリットがあるよう設計されている。「たとえば、2アールの畑ではとうもろこし約600本が収穫可能で、市場で販売するとおよそ10万円程度の売上が見込まれます。『千菜一遇 農en』では、その2倍の報酬を農家へ支払うことで、Win-Winになるようにしているのです」と山口氏は語る。さらに、大治が企業と農家の間に立ち、業務管理やアテンドを補助する体制を取っているため、農家にとっても負担が少ない。
同社の新たな取り組みとしては、青果物を事前に予約し、指定の場所で受け取ることができる消費者向けのサービス「ゆにくる」も挙げられる。このサービスの特徴は2つあり、1つ目は、朝採れのとうもろこしや搾りたての牛乳など、「一番おいしいタイミング」で収穫された商品を高鮮度のまま消費者へと届けられること。2つ目は、事前予約が必須であることから、流通在庫が不要のため、売れ残りリスクを回避できることだ。現在、「ゆにくる」の趣旨に賛同するマンションなど、複数の施設が受け取り拠点として機能している。「今後は、大田市場から近い港区などを中心として、受け取りポイントを増やしていきたいです」と山口氏は語る。
また、大治はシンガポールや香港への定期的な出荷も行っている。現地ではMade in Japanの農産物へのニーズが高く、マスカットが1万円で販売されても売れるほどだ。「卸先の高級スーパーからは、『普段東京で売っているような商品を店頭に出していきたい』とご相談いただいています」と山口氏は言う。
※2:もみがら。稲の実の外皮。籾米をついて玄米を得たあとの殻。
※3:Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会的責任。企業が事業活動を通じて社会や環境に配慮し、ステークホルダー(利害関係者)に対して責任ある行動をとることを指す。
農家に市場ニーズの高い品種を提案。農家との協業と付加価値創出への取り組み
大治は「東京野菜」のブランディングを進める上で、農家との密なコミュニケーションに基づく協業体制を築いている。「農家の方々は、どのような作物を育てればよいのか、またどういった品種が市場から求められているのかと悩んでいました。そこで、当社はとうもろこしや枝豆など鮮度が命の商品を中心に、どの品種が望ましいかを生産者と連携しながら提案してきたのです」と山口氏は述べる。
業界でも先んじてブランド育成やインフラ整備に取り組んできた大治。しかし、そんな同社を取り巻く環境は極めてシビアだ。物流コストの高騰や人手不足が深刻化している上、価格転嫁が難しく、既存取引の中では利益を出しづらい状況が続いている。中間業者への風当たりも強い。その分、同社は新規事業やブランド価値の向上による付加価値創出に励んでいくという。「特に、有機野菜は消費者の認知や需要が高まれば、小売店での取扱量が増える可能性はあります」と山口氏は期待を寄せる。
山口氏は「鮮度の高い商品を、効率的な物流体制のもとでお届けしつつ、長期的に顧客満足度とブランド力を高めていくことで利益を上げていきたい」と締めくくった。