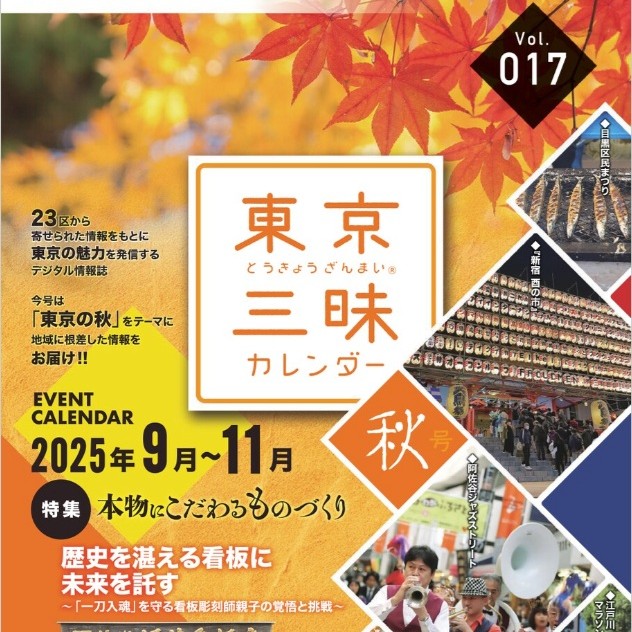2025年8月7日更新
株式会社東あられ本鋪
| 所在地 | 東京都墨田区亀沢2-15-10 |
|---|---|
| 代表者 | 小林 正典(代表取締役会長) |
| 資本金 | 7,800万円 |
| 従業員数 | 97人 |
| 設立年 | 1910年 |
| 企業HP | https://www.azuma-arare.co.jp |
都営大江戸線の両国駅から徒歩約5分。墨田区・北斎通りに本店を構えるのが、米菓の製造・販売を手がける「株式会社東あられ本鋪」だ。1910年の創業以来、あられやおかきを作り続けている同社は、卸先である百貨店の業績不振やお中元・お歳暮需要の変化などの課題に直面してきた。
突破口を見出すために注力しているのが、金芽米®(※1)を使用したこだわりの逸品「釜処 枡恵美(かまどころ ますえみ)」や葛飾北斎の作品をあしらった「北斎シリーズ」、洋菓子「あずま米菓堂」といった新ブランドの展開だ。多様な商品ラインナップにより幅広い顧客のニーズに応えるかたわら、同社は顧客に対するきめ細やかな接客・販売を心掛けることで、地域密着の老舗米菓店として、ゆるぎない地位を確立している。
※1:きんめまい。玄米の胚芽の部分を80%以上残して精米したお米のこと。
米菓の卸から百貨店を中心とした直売へ転換。ANAの機内食に採用される

高い人気を誇る東一福
第二次世界大戦前までは、仲間卸や問屋へおかき・あられを卸していたという東あられ本鋪。昭和30年代に直売への転換を図り、百貨店や駅ビルへの出店を皮切りに、主に西武百貨店とそごうを中心として東日本へ展開していった。
「当時は法人のお中元・お歳暮需要が大きく、贈答用の箱物が売上の7~8割を占めていました」と、4代目にあたる小林氏は振り返る。この直売展開の中で転機を生んだのが、1990年にANAの機内食として採用された「東一福」だ。一つの袋に数種類のおかきが詰まった「東一福」のスタイルは当時としては珍しく、乗客からの反響が非常に大きかったという。「そのため、『東一福』を小売り用に商品化し、通信販売を中心に個人のお客様への販売を開始したほか、百貨店でも『甑(こしき)』という名称で販売したころ、またたくまに人気となり、当社の看板商品へと成長しました。」と小林氏は語る。
そんな中、大型テーマパークのお土産品としての引き合いがあり、OEM(※2)も始めたという同社。定番商品として、年間4~5億円の売上を記録するほどの成功を収めたが、約8年で撤退したという。
「監査基準が非常に厳しく、工場査察やトラブル発生時の負担が重くのしかかりました。また、当初は自社商品をそのまま販売する形だったものが、次第にオリジナル商品の開発を求められるようになったことも一つの要因です。このままでは、原材料の制約などから『自分たちの作りたいもの』を作れない。悩んだ末、『いいものは自分たちで直接売りたい』と原点に立ち返り、OEMからの撤退を決断しました」と小林氏は述べる。
同社を悩ませたのはそれだけではない。2005年頃に入ると、百貨店業界が業績不振に陥る。加えて、法人のギフト需要が減少し、次第に個人へシフトするに従ってお中元需要は激減。東あられ本鋪の売上も低迷し、百貨店からの撤退を余儀なくされた。小林氏は「従業員の肩を叩くことは本当につらかった。ですが、実店舗と通信販売での直売事業のみに事業を縮小したことにより、人件費を含めた経費が大幅に削減され、会社を存続させることができました」と吐露する。
※2:Original Equipment Manufacturer の略。他社ブランドの製品を製造すること。
個人の幅広いニーズに応える味やブランド、パッケージの開発に注力

北斎シリーズの一つである北斎揚げ
かつて主力だった箱物の売上は現在、3~4割にまで減少。その分、袋菓子などの個人消費向け商品の需要が高まっている。そのため、東あられ本鋪は個人の幅広いニーズに応える新しい味やブランドの開発に、積極的に取り組んでいるという。「パクチー味やトリュフ塩味など、バラエティに富んだフレーバーを揃えています。ここまでバラエティに富んだ商品ラインナップ他社にはあまりないと思います」と小林氏は言う。
これらの多様なシリーズ展開は、ギフト用途だけでなく、日常的に購入してもらえるような商品を目指しているためだ。チャック付きの袋や、食べきりサイズの小袋など、顧客の消費スタイルに合わせてパッケージも工夫して販売している。
不易流行・温故知新。「良いもの」に対するこだわりはそのままに、時代に合わせて戦略を変えていく。その理念のもとで2023年に生まれたのが、「原点回帰」をテーマに素材への究極のこだわりを追求したおかき、「釜処 桝恵美」だ。金芽米®を使用し、化学調味料をほとんど使わないシンプルな味付けにすることで、お米本来の甘さと美味しさを最大限に引き出している。「健康志向のお客様をターゲットとし、価格帯も高めに設定しています。最終的には60個入りの箱をご購入いただきたいため、あえて廉価版は作っておりません」と小林氏は話す。
さらに、新たな挑戦として、フィナンシェやクッキーなどに米粉を使用した洋菓子ブランド「あずま米菓堂」を立ち上げた。米菓の「辛い」軸だけでなく、洋菓子の「甘い」軸でも米を活用することで、商品の幅を広げ、顧客の来店頻度を高めることが狙いだ。「米菓の賞味期限は3か月~6か月ほどなのに対し、洋菓子は長くても1か月です。より頻繁な来店を促すことで、顧客との接点を増やし、米菓の購入にも繋げたいと考えています」と小林氏は力を込める。
また、同社の代表的なブランドとして、パッケージに地元ゆかりの葛飾北斎の作品デザインをあしらった「北斎シリーズ」が挙げられる。両国本店の位置する墨田区亀沢が葛飾北斎生誕の地であることから、葛飾北斎の知名度を上げて地域を盛り上げたい、との思いで開発したという同商品は、その特徴的なパッケージから個人向けの手軽なお土産物として人気を博している。その他にも「北斎通りまちづくりの会」として年に1度「北斎祭り」を開催しているほか、両国本店でコラボ寄席を実施するなど、地域活性化に尽力する小林氏。「北斎通りを中心として、両国を面で発展させていきたい」意気込みを語った。
「100人以上の顧客を記憶する」など、きめ細やかな接客・販売を行う

丁寧な接客を心掛ける
原材料にこだわり「良いもの」を作り続けるためには、価格転嫁は欠かせない。「現在、お客様の負担を考慮しながら段階的に値上げを行っています。ただ、高くても買っていただくためには、丁寧な接客を心掛け、お客様とより強固な関係を構築しなくてはなりません」と小林氏は主張する。同社の販売部では月に1度の割合で外部のコンサルタントを招き、「顧客をいかに大切にするか」を学んでいるという。
「理想は、お客様の顔と名前を一致させること。なかには100人以上のお客様を記憶しているスタッフもいます。このような取り組みを通じて、『来店してよかった』と感じてくださるお客様を増やしていきたい」と小林氏は言う。同社は、直営店3店舗だけでなく通信販売でも販売時の御礼メールなどでのきめ細やかな対応を徹底し、顧客に寄り添った丁寧な販売を心がけている。
「当社ではお客様に『東カード』という会員カードを発行しています。カード情報を分析したところ、お客様の6~7割が地域住民だと分かりました」と小林氏が言及する通り、東あられ本鋪は地域密着型の接客・販売を積み重ね、リピーターの獲得に成功している。
時代ごとに売り方も変われば、商品も、パッケージも変わる。しかし、同社が変わらず大切にしているのは「最終的に買ってくださるのは、全てお客様である」という理念だ。その姿勢を忘れず、地域に根差した事業運営を続けてきた結果が、115年にわたる歴史として刻まれている。