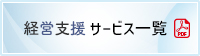~流通サービス業の実践的経営改善ガイド~
参考 流通・サービス業の現状と課題
3.流通・サービス業における内部環境と外部環境
ここまで述べてきた現状と課題を整理し、事業戦略を考えていく上では、自社でコントロールが可能な内部環境(自社内の状況)と、自社でコントロールすることができない外部環境(社会の状況など)に分けて考えていくことが効果的である。
外部環境とは、人口動態、政治、経済、自然、社会、技術、文化という視点で情報を整理するもので、消費者のライフスタイルなど世の中の動きも含み、自社でコントールすることが難しいものである。一方、内部環境は、自社の経営能力、生産能力、マーケティング能力、情報収集能力、人材能力、財務能力など社内にある資源であり、自社でコントールができるものである。
外部環境と内部環境の両方を組み合わせて、経営戦略を考えることを一般的に「経営環境分析」という。ここでは、簡単にできる「経営環境分析」の手法の一つであるSWOT分析を使い、状況を整理していきたい。
SWOT分析は、自社をとりまく外部環境と自社の内部状況を整理し、戦略立案や意思決定のヒントを得るためのフレームワークである。SWOT分析では、内部環境、外部環境の両方で、自社にとってプラスとなるポジティブな情報とマイナスとなるネガティブな情報に分けて情報整理を行う。このうち、内部環境でプラスの情報は自社の「強み」であり、マイナスの情報は自社の「弱み」である。外部環境では自社の事業の追い風になるようなプラスの情報は「機会」、逆にマイナスに働きそうな情報は「脅威」として整理する(図表14)。
これらの情報の整理が完了したら、SWOT分析では、組み合わせで今後の方向性を検討する。例えば、O「機会)を最大限活かすために「強み」と掛け合わせてみる、あるいはT「脅威)への対処として「弱み」を補完する施策を検討する、などである。このようにSWOT分析は、Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の4つに整理した情報を掛け合わせて、今後の方向性を検討する分析手法である。古典的な手法でありながらも、シンプルで有効性が高く、現在でも多くのビジネスシーンで用いられている。
では、ここから流通・サービス業の現在の状況を整理していく。まずは内部環境から検討する。SWOT分析において、内部環境分析は自社の「強み」と「弱み」を整理することである。しかし、いきなり自社の強みと弱みを考えてみよう、と言われても戸惑うことも多いと思われる。そして実際のところ、各事業者によって内部環境は大きく異なっている。そのため、ここでは「どのような視点で」内部環境を検討するべきかについてマーケティングを中心に説明したい。
【内部環境分析】Strengths(強み)とWeaknesses(弱み)の考え方
自社の強みと弱みを考える時の切り口として、マーケティングの4P、7Pの視点で考えてみると検討がしやすくなる。4Pの視点であれば以下のようになる。
Product(製品)
自社が提供する商品やサービスが強みではないか?強みであると思う場合、どういった点が他社よりも優れているだろうか?などを検討する。一方、商品のスペックなどで改善するべき課題がある場合は、弱みに分類される。
Price(価格)
価格優位性はあるだろうか?販売価格は強みであるか?といった価格の面、あるいはコストの面から強みと弱みを考える。どうしても下げられない原価がある場合などは、弱みに分類される。
Place(流通)
販売方法や販売チャネルは自社の強みなのか、弱みなのか?店舗は強みであるが、WEB対応が遅れている場合、EC対応は弱み、ということもあり得る。
Promotion(プロモーション)
広告宣伝や販売促進がどの程度実施できているか、といった内容だけではなく、最近では、SNSを活用した顧客とのコミュニケーションなどまで幅広い範囲で検討するべきものである。強みと弱みの両面から広告宣伝や顧客コミュニケーションを検討してみる。
ここにサービス業向けにさらに3つのPを加えたものが7Pと呼ばれており、サービス業のマーケティングを考えるための切り口として使われている。
People(人)
従業員そのものや、その従業員のおもてなし能力や接客能力などが強みになっていないか。あるいは自社独自の教育プログラムなども強みとなる。また、逆に従業員が定着しない、人手不足・人材不足が課題となっている場合は弱みに分類できる。
Process(プロセス)
どのような方法でサービスを提供するのか。業務のプロセスや販売プロセスを考えたときに、それが自社の強み・弱みとなっていないかを検討する。例えば、産地からの直接の仕入を行って消費者の支持を受けている場合、プロセスとしての「産地直送」が強みとなっていると言える。
Physical Evidence(物的証拠)
サービスが提供されたり、顧客と触れ合ったりする環境を含め、サービスに付随するあらゆる有形のモノを指す。例えば、あるカフェがお洒落な内装で人気があった場合、「お洒落な内装」がPhysical Evidenceに該当し、強みとなっていると言える。
以上、ここまで自社の「強み」と「弱み」を検討するための切り口について、マーケティングの視点から述べてきた。しかし、他にも環境対応への取り組みや他産業との連携など、無数の切り口が存在している。そういった意味では、自社内で従業員や役員と一緒に、複数人で自社の強みと弱みについて検討してみることも効果的である
ただ、どうしても自社の強みが見えてこない、といったことも考えられる。その時は競合する事業者と比較したり、過去の自社から良い方向への変化が無かったかを考えてみたりして欲しい。比較することで、自社の特徴や長所が見えてくることもある。加えて、今までの顧客からの評価を振り返ることも効果的である。どんな点が顧客から評価された、褒められたかを複数人で話し合ってみても良い。
【外部環境分析】Opportunities(機会)とThreats(脅威)の考え方
続いて、外部環境について考えてみたい。自社を取り巻く外部環境についても、競合情報などは当然ながらそれぞれの事業者によって競合相手が異なるため内容が異なるが、消費者の動向や大きな社会情勢は共通のものも多い。よって、ここからは主に多くの流通・サービス事業者にとって共通の「考慮するべき情勢」についてOpportunities(機会)とThreats(脅威)の視点から考えてみたい。
【外部環境分析】Opportunities(機会)
ここまで流通・サービス業を取り巻く課題について論じてきたが、課題だけではなく、新しいマーケットニーズの出現や、小規模事業者でも活用できる技術など、新たなビジネスチャンスとなる変化=Opportunities(機会)も生まれており、常にアンテナを張っておきたい。もちろん機会も検討の切り口は無限に存在しているが、ここでは、以下の4つの視点で「機会」を整理したい。
1社会・ライフスタイルの変化
- コロナ禍での移動規制の影響もあり、消費者の地域密着志向や「小さな店」への再評価が進んでいる。
- ふるさと納税によって、地域の特性を核とした商品やサービスのマーケットが拡大している(東京都は他の地方に取られがちであるが、東京の特徴を活かした商品やサービスの展開余地もある)。
- 高齢者や子育て世帯向けの買い物だけではなく、生活支援や教育(生涯教育、知育等)といったサービス需要も増加している。
- リモートワークの普及や働き方改革を背景に、ワークライフバランス志向が強まった結果、自宅近隣で買い物やサービスを受ける機会が拡大している。
2技術の発展
- キャッシュレス決済やPOSの低コスト化が進み、クラウド型のサービス等でレジシステムなども格安で導入できるようになっている。
- 低コストで取り組めるSNSを活用した集客や、ECサイトを活用した販路拡大の可能性が広がっている。
- 多種多様な業務改善のためのクラウド型DXツールが提供されており、中小・小規模事業者でもローコストで業務の効率化を図れるようになっている。
- 人手不足解消のための短時間でのパートタイム雇用ができるサービス(タイミーなど)も登場し、人が集まる都内では活用できる可能性が高い。
3制度・支援策
- 中小企業庁や東京都による公的支援制度や補助金が充実している(例:事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金など)。
- 買い物困難者支援や、地域商店街振興施策との連携による地域との連携機会が増加している。
- 国として人材育成のためのリスキリングの制度や補助の充実が進んでいる。
- いわゆる下請法の改正や「パートナーシップ構築宣言」の拡大など、価格転嫁・交渉がしやすい環境になりつつある。
4地域ブランド・観光産業との連携機会
- インバウンド需要が増加している。特に東京都は多くの外国人が来訪する都市の1つとなっている。
- 地域資源を活かした商品開発や観光誘客への連動(地域産品への興味関心の高まり)が見込める環境になりつつある。
- ふるさと納税との連携(返礼品の販売機会、返礼品としての宿泊クーポン等)機会も増加しつつある。
【外部環境分析】Threats(脅威)
「2.生産性と賃金の低さをはじめとした流通・サービス業の課題」で整理したように、昨今は経営環境の変化が速く、自社の経営に脅威となる事項については早急な把握と、柔軟な対応が求められる時代となっている。ここでは以下の5つの視点から代表的な「脅威」となりうる外部環境を整理したい。
1競争環境の激化
- 大手のチェーンストアやディスカウント店が台頭してきており、中小・小規模の流通・サービス業においては価格競争にさらされている。
- 特に店舗販売を行う事業者は、EC・宅配サービスとの利便性競争が発生しており、店舗で購入するための付加価値を考える必要がある。
- フランチャイズ型のビジネスモデルも広がっており、気軽に事業に取り組める反面、商品やサービスでの差別化が難しくなる可能性がある。
2人材・労働問題
- 現在、多くの業種・業態では慢性的な人手不足・人材不足状態にある。求人募集をかけても応募自体が少ないなど、人材確保が難しくなっている。
- 転職やキャリアチェンジが一般化し、人材の流動性が高くなった結果、人材定着が難しくなりつつある。
- 賃上げが政策課題となっていることに加え、最低賃金の上昇もあり、企業においては人件費の上昇に繋がっている。
3経済・物価動向
- 長期の円安や地政学的リスク、アメリカの関税政策などの外的要因により、仕入コストが上昇している。
- 物流2024年問題による物流コストの高騰や、エネルギー(光熱費)コストの増加が顕著となっている。
- 物価高騰などの影響によって、消費者の節約志向が強まっている。
- 家庭における可処分所得の割り振りが変わりつつある。食費や生活費は節約する一方で教育費などは増加している。
4災害・感染症等のリスク
- 地震や洪水などの災害から、新型コロナウイルスのような感染症まで、様々な突発的リスクが発生する時代となっており、リスクに対する備えが必要となっている。
- 都内の流通・サービス事業者において、インバウンド需要は非常に大きなチャンスであるが、コロナ禍の教訓を踏まえると、観光依存型経済の不安定さには注意が必要である。
5人口動態の変化
- 商圏の高齢化が進み、高齢者向けの商品・サービスの展開が求められつつも、将来の消費の中心となる若年層の取り込みも課題となっている。
- 都内においても、今後23区外を中心に人口減少と少子高齢化によって、消費量の低下、顧客の移動困難な状況が生まれると予想される(買い物困難者など)。
以上、ここまで外部環境分析として、「機会」と「脅威」について一般的なものを整理してきた。ここから言えることは、内部環境分析も同じであるが、「強み」と「弱み」、「機会」と「脅威」は表裏一体であるということである。インバウンド需要は大きな機会であるものの、それに依存してしまうと脅威(リスク)にもなってしまう。既存顧客との強いネットワークは自社の強みとなるものであるが、それに依存してしまうと新規顧客が獲得できていない弱みとなってしまう。
しかし、マイナスの要素とプラスの要素が表裏一体であるからこそ、ピンチをチャンスに変えることができるとも言える。ここからは「弱み」や「脅威」という自社にとってマイナスの要素にどのように対応していくべきか、整理した内部環境と外部環境をクロスさせるSWOT分析で見ていきたい。

- はじめに
- 好事例に見る流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(実践編)
- 流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(理論編)
- 流通・サービス業の現状と課題