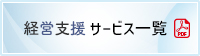~流通サービス業の実践的経営改善ガイド~
参考 流通・サービス業の現状と課題
1.人手不足・物価高騰時代における流通・サービス業の現状
2025年現在、物価の高騰が続いている。事業活動に必要な様々なコストが増加している一方で、その増加コストを自分たちの商品やサービスの価格に転嫁することができず苦しんでいる流通・サービス事業者は少なくない。
実際に政府の統計を見ると、東京都の最低賃金は2002年には708円/時間であったが、2024年には1,163円/時間となった。さらに消費者物価指数は2020年の平均を100とした場合、124.8と2割以上高騰している。また、原材料コスト、人件費以外にも光熱費、物流費なども高騰している。
こうした物価の高騰は様々な産業があるなかでも、特に流通・サービス事業者を苦しめる結果となっている。帝国データバンクが公表している2024年度(2024年4月~2025年3月)の倒産件数を業種別にみると、『サービス業』(前年度2,187件→2,638件、20.6%増)が最も多く、次いで、『小売業』(同1,874件→2,109件、12.5%増)ということであり、流通・サービス事業者が厳しい状況に置かれていることが見て取れる。倒産の主因としては、「販売不振」が8,261件(前年度7,027件、17.6%増)で最も多く、全体の82.0%を占めている。
流通・サービス業は、小売業やサービス業など消費者と直接相対する事業者、そしてそういった事業者を支える卸売業や広告業、士業、ITサービス業等である。物価高騰によって消費者の消費マインドが低迷している今、SNSやインターネットの普及により、価格情報が消費者間で共有されやすいことも相まって、事業コストが高騰しているにもかかわらず、なかなかそれを商品やサービスの価格に転嫁することが厳しい状況にある。価格競争と利益創出の間で多くの経営者が頭を悩ませているのである。
こうした状況の中であるからこそ、流通・サービス事業者が事業を継続しながら更なる発展を目指すためには、経営資源の的確な配分が重要である。そのためには、事業ドメインの再定義が重要となる。事業ドメインを再定義することによって、自社の事業領域や市場等が明確化され、経営資源の選択と集中が可能となり、より戦略的な商品・サービスの展開を通じた事業継続・発展が期待できるのである。
また、人手不足・人材不足が経営課題となっているなかでは、業務プロセスの見直しと効率化が急務になっている。DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務の効率化はもちろんのこと、自社事業の見直しと、業務のスリム化も重要な課題となっている。これは自社内で実施する必要が無い間接業務などは外部へ委託することで業務のスリム化と社内人員の工数削減を行い、そこで浮いた工数を自社の事業において重要な部分(新商品・新サービスの展開等)へ投資することで成長を図っていくものである。
厳しさを増す経営環境の中で利益創出を図っていくために、自社のドメインをどのように定義し、売上を上げるのか。コスト削減と人手不足をカバーするための業務のスリム化などをどのように考えていくのか、今こそ考えるべきタイミングである。

- はじめに
- 好事例に見る流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(実践編)
- 流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(理論編)
- 流通・サービス業の現状と課題