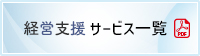~流通サービス業の実践的経営改善ガイド~
第2部:流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(理論編)
3.4つのイノベーションによる経営改善
以上、ここまで流通・サービス業の特徴やアンケート結果から、経営改善に向けたポイントや、既に流通・サービス事業者によって実施されている施策まで整理してきた。ここまでの議論を踏まえ、ここからは流通・サービス事業者の経営改善に向けたアプローチについて、4つのイノベーションの視点からまとめていく(図表5)。
視点①:プロダクトイノベーション
プロダクトイノベーションとは、企業が新製品やサービスを開発し、差別化を図るイノベーションを指す。既存の製品やサービスには無い新しい価値を提供することで、市場における競争優位性を確立するものである。この視点に立てば、流通・サービス業では以下のような取り組みが考えられる。
-
希少性・独自性が高く、競合と差別化できるような商品・サービスを提供することで、価格競争にさらされないビジネスを行う。職人的な技術やスタッフの接客技術、生産量が少量に限定されるもののなど、大手企業では模倣が難しい取り組みが望ましい。
(例)他にはないオリジナルのメニューを持つレストラン。 -
新たな商品・サービスを開発することで、今までターゲットとしてこなかった新しいマーケットを開拓、付加価値を高めて価格転嫁を行う。流通・サービス業として顧客ニーズが把握しやすいこと、企業規模が小さいことによる小回りの良さを最大限活用する。
(例)酒蔵がカフェを開き、日本酒を使ったスイーツや甘酒を提供する。 -
競合が少ないニッチな市場に新しい商品・サービスを開発することで参入する。ニッチなマーケットは、大手企業の参入が少なく、中小・小規模事業者でも優位性を築きやすいため。
(例)中古車販売店が電動キックスクーターを取り扱う。 -
地域資源を活用した商品・サービスを開発する。顧客との物理的・心理的距離が短く、地域密着度が高い流通・サービス業の特性を活かし、地域資源を上手に活用することで大手企業との差別化を行う。
(例)地元の特産品を使ったオリジナルパンの開発と販売。
しかし、プロダクトイノベーションを考えるあたり、新製品開発における不確実性(開発が技術的問題でとん挫したり、競合に先を越されたりするなど)や、失敗(全く売れないなど)のリスクを最小限に抑えるための対策も検討しておく必要がある。具体的には、市場調査を徹底し、顧客のニーズを確実に把握することや、技術的な課題への対応、競合商品・サービスの徹底的な分析と差別化策の検討などがあげられる。
視点②:プロセスイノベーション
プロセスイノベーションとは、製品やサービス自体の変化ではなく、それらの生産や流通の過程を改善し、効率化・コスト削減・品質向上を図るものである。この視点に立てば、流通・サービス業では以下のような取り組みが考えられる。
- 事業をスリム化することで事業コストの低減を図る。従業員数が少ない中小・小規模事業者だからこそ、アウトソーシング等により自社の業務プロセスの中にあるムリ・ムダを無くすことが特に有効である。
- DXにつながるソフトウェアやAIを活用し、人件費削減と生産性向上の両立を図る。ここで重要なポイントはDXを行うことやAIを活用することが目的ではなく、それによって浮いた工数(人手)や得たデータ等を別の業務・事業に活用することが目的である点である。これは人材活用の面から見れば、組織イノベーションに分類されうるほか、新商品・サービス開発の面から見れば、プロダクトイノベーションにも分類されうる。
当然ながら、プロセスイノベーションにもリスクがある。新しい業務プロセスを導入する場合、切り替え時におけるオペレーションの混乱や、業務部門ごとの責任範囲が曖昧になることでのミスの発生など、予期せぬ問題や損失が発生するリスクである。これらの対策としては、業務プロセスを見直す場合のリスクを特定し、その影響を分析・評価した上で、回避、軽減、転嫁、受容といった対応策を検討・実施することがあげられる。とりわけ、アウトソーシングを行う場合は、委託先の選定の段階でリスク対応を考えておく必要がある。
視点③:組織イノベーション
組織イノベーションとは、企業や組織が自社の仕組みや構造、文化などを改革し、新たな価値を生み出すことや、イノベーションを起こせる組織を構築していくことを指す。この視点に立てば、流通・サービス業では以下のような取り組みが考えられる。
- 様々な改善を社内で起案・実行・管理できる体制を構築する。とりわけ流通・サービス業の中小・小規模事業者は大手企業よりも社内の人数が少なく、現場から経営者までの意思疎通がはかりやすい特徴がある。そのため、急速に変化する外部環境に対応するべく、提供する商品・サービスから社内の業務プロセスまで、大企業よりも速い速度で柔軟に改善に取り組める組織体制を作ることで競争力の向上につながる。
- 現場への人材配置と決裁権の付与を行う。上述したように流通・サービス業は顧客とのコンタクトが他業種よりも多いという特徴があるため、店頭や受付なども含め、顧客と相対する現場での迅速な意思決定を可能とする仕組みづくりが競争力の向上につながる。
- 社外とのネットワークを構築する。経営環境が不確実性を増している現在、企業として競争するべきところは競争し、自社の商品やサービスを磨き上げる一方で、事業のなかで協調し、連携した方が互いにメリットになる部分は他社と手を取り合っていく協調・協働の考え方が重要となっている。この「競争と協調」は、規模の経済性がはたらきにくい中小・小規模事業者が自らの専門性や特殊性を強みとし、ネットワークの経済性を発揮するべく他社と連携して成長していくために重要な概念であり、SDGs等の環境対応を考えていく上でも役に立つ考え方である。
組織の変革や新しい取り組み(イノベーション)を進める際にも、予想されるリスクを事前に把握し、その影響を最小限に抑えるための対策を講じることが必要である。組織イノベーションのリスクとしては、対外的な組織の評判低下や、従業員のモチベーションの下落、離職者・退職者の発生などが考えられる。対策としては、組織内でのコミュニケーションを強化することや、従業員への経営理念やミッション、中長期計画の共有と理解促進などがあげられる。
視点④:マーケティングイノベーション
マーケティングイノベーションとは、顧客ニーズを深く理解し、それに基づいて新たな製品やサービス、あるいは販売方法などを開発することで、より高い顧客満足度と売上向上を実現するものを指す。この視点に立てば、流通・サービス業では以下のような取り組みが考えられる。
- 企業そのもののブランド力を高め、その付加価値を顧客に認識してもらうことで価格競争を回避する。中小・小規模事業者にとっての「ブランド力」とは、一般的に認知度の高い「(高級)ブランド」ではなく、「この地域の、この商品・サービス」などといった限定的な範囲における高い認知度・イメージのことであり、そういった商品・サービスのブランド力は、それを企画・販売する企業のブランドと強い関係性を持つ。ゆえに、自社にとって必要な商圏内で自社名や屋号を顧客に知ってもらったうえで、自社の評判を高めることが、自社の商品・サービスのブランド力を高めることにもつながり、結果として価格競争を回避できる可能性が高まる。
-
顧客とのコミュニケーションに注力する。顧客とのコンタクトが多く、企業として小回りが効く中小・小規模の流通・サービス事業者にとっては、極めて重要な取り組みである。具体的に、取引形態の種別(BtoB/BtoC)によって考えるべき視点を以下に示す。
-
BtoBの場合、顧客との対話において値上げ交渉を実施することが重要である。その時、値上げをする理由(原価高騰、人手不足など)について説明し、理解してもらうことを意識する必要がある。また、物流費などの外部へ支出する費用の高騰による価格転嫁を目指す場合は、実施する内容ごとに費用を示すメニュープライシング(※)が有効である。例えば、引き取りであれば〇〇円、関東までの送料込みであれば〇〇円、引き取りまでの保管が1ヵ月を超えると〇〇円のようなイメージである。転嫁すべきコストについて、顧客と議論するための材料としてもメニュープライシングは有効である。
※メニュープライシング:提供するサービスレベルや物流コスト等に応じて複数の価格を設定すること。 - BtoCの場合、顧客とのコミュニケーションを通じて、自社商品・サービスの価値を訴求し、消費者に理解してもらうことで価格転嫁を実現するほか、消費者とのコミュニケーションを通じて、そのニーズを拾い上げ、商品・サービスの仕入や開発に活用することが重要である。プロダクトイノベーションで触れた希少性・独自性が高く、競合と差別化できるような商品・サービスを新たに考えていく場合、顧客ニーズの把握は必要不可欠であり、そのためにも顧客とのコミュニケ―ションは重要である。
-
BtoBの場合、顧客との対話において値上げ交渉を実施することが重要である。その時、値上げをする理由(原価高騰、人手不足など)について説明し、理解してもらうことを意識する必要がある。また、物流費などの外部へ支出する費用の高騰による価格転嫁を目指す場合は、実施する内容ごとに費用を示すメニュープライシング(※)が有効である。例えば、引き取りであれば〇〇円、関東までの送料込みであれば〇〇円、引き取りまでの保管が1ヵ月を超えると〇〇円のようなイメージである。転嫁すべきコストについて、顧客と議論するための材料としてもメニュープライシングは有効である。
- 顧客ネットワークを活用する。今の消費者はSNSなどを通じて友人・知人と様々な情報を気軽に共有できるようになっており、自社の紹介を消費者にしてもらうことで、その消費者とつながっている友人にアプローチできる。SNSへの投稿で粗品をプレゼントしたり、写真映えする商品やサービスを提供したり、友人へ情報をシェアしやすくする工夫も考えたい。また、純粋な友人紹介キャンペーン(紹介者にも被紹介者にもインセンティブがある)のような取り組みも効果的である。当然、企業間取引でも顧客ネットワークの活用は有効で、他の担当者や関係する事業者を紹介してもらうことで、新規顧客の発掘につなげることができる。顧客ネットワークを通じて紹介してもらうことは、紹介者による信頼性の担保、紹介者の面子を守るという意味での競合排除の意味で、最も効率的かつ効果的な顧客開拓手段と言える。
- 社会課題の解決に取り組む。マーケティングの視点でも、企業活動の視点でもこれから必ず求められることの1つである。企業として事業活動を営みながら、社会課題の解決に取り組んでいくことは、今後の新たな企業価値の創出や、競争力につながっていくと考えられる。社会課題への取り組み、というと非常に大きな話で大変な取り組みに聞こえるが、流通・サービス業の場合、地域密着である強みを活かし、身近な社会課題の解決から取り組んでいくことができる。例えば、地元で使われずに捨てられてしまっている資源などがあれば、それを活用した商品・サービスを開発し、地元の産物の活用と廃棄物の削減を両立するような取り組みである。
新しいマーケティング手法や戦略を導入する場合、市場の反応が予測困難であることも多く、新しい技術や手法の導入に失敗する可能性もあるため、予期せぬ事態や失敗のリスクを最小限に抑えるための対策を講じておくことが必要である。具体的には、顧客や消費者を理解するための市場調査を徹底することや、広告宣伝などは最小の費用と工数で小さくテストを行い、その結果を見て大きく展開するようなアプローチ(段階的な導入)をとること、実施したマーケティング施策のPDCAサイクルの高速化と柔軟な対応策の準備などがあげられる。
以上、4つのイノベーションについてまとめてきたが、新たな施策や事業を検討・推進する際は、法的リスク管理が不可欠である。関連法制度の確認、コンプライアンス体制の整備等、取り組みと併せて常にリスクに備えておく必要がある。

- はじめに
- 好事例に見る流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(実践編)
- 流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(理論編)
- 流通・サービス業の現状と課題