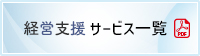~流通サービス業の実践的経営改善ガイド~
第2部:流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(理論編)
1.流通・サービス業の特徴と経営改善のポイント
ここでは、流通・サービス事業者が取り組むべき経営改善の具体的なアプローチについて考えたい。ここで考える具体的な経営改善のアプローチや改善に向けたポイントは、第1部で具体的な事例から学んだ経営改善の取り組みを自社に落とし込む際にも参考になるものである。
経営改善のアプローチやポイントを考える上で、はじめに流通・サービス業が他の業種と何が違うのかを整理したい。その特徴にこそ、アプローチを考えるヒントがあるからだ。
まず大きな特徴としては「顧客との距離の近さ」と「ニーズ対応のレスポンスの早さ」が挙げられる。下図は、製造業と流通業、サービス業の違いを顧客(消費者)とのコンタクトの頻度や濃度の高さ、および販売する商品等に触れることができるか(触知性)で概念的に整理したものである(図表1)。
製造業は一般的にモノを作るため、触知性が高く(実態があるものを扱う)、販売においては卸売業や小売業を挟むため、顧客との直接のコンタクトは低くなる。一方で、サービス業は消費者に直接向き合って役務を提供する業種であるため、顧客とのコンタクトが高く、提供するサービスも無形のものであることも多いため、触知性は低い。流通業は、小売業と卸売業で多少の違いはあるものの、基本的に製造業とサービス業の中間に位置する。
ここでのポイントは、触知性が低く、顧客とのコンタクトが高い業態は、顧客の意見を直接聞くことができ、かつ提供する商材を柔軟に変更できる点にある。すなわち、製造業の場合、新たに顧客ニーズを把握し、商品を開発して販売するまでには多くの予算と時間が必要になるのに対し、流通業の場合は顧客の声を店頭で直接聞いたうえで、顧客のニーズにあった商品を探し、仕入れて販売することでレスポンス良く顧客のニーズに対応でき、サービス業の場合も、無形財であるため、直接お客様の声を聞き、それに合わせてサービスをすぐに見直すことができるのである。
そしてもう一つの特徴は、「地域特性の活用のしやすさ」である。そしてそれを可能にしているのが、顧客との距離が近いがゆえの地域性の高さ、いわゆる地域密着である。小売業では、近隣の商圏の顧客に合わせた品揃えが基本となっており、商圏単位で地域に合わせる意味で地域密着であると言える。サービス業についても、サービス内容を商圏の顧客に合わせること、あるいは宿泊業・ホテル業などの場合は近隣の観光地や名所を活用したり、連携したりするため、地域密着と言える。
以上を踏まえたうえで、流通・サービス業の経営改善のポイントを考えていきたい。流通・サービス業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、最も重要ポイントは、利益の創造である。少子高齢化が進む日本においては国内の消費額・消費量は多くの商品・サービスで長期的には下落していってしまう。国内マーケットが縮小していくなか、ITサービスなどグローバルに展開できる事業や輸出事業を除き、顧客との距離が近く、地域密着型のビジネスである流通・サービス事業者が売上高を上げ続けることは難しい。そのため、これからは利益に注目した経営が求められる。
利益は当然、「販売額」―「コスト」である。よって、利益を上げるためには、販売額を上げるか、コストを削減する必要があり、すなわち、価格転嫁・付加価値向上と、コストを削減するための生産性向上が重要となる、ということである。事業コストが上昇している現在、商品やサービスの価格にそれらを転嫁できなければ利益創出は難しい。利益経営が求められる現在だからこそ、価格転嫁は重要な経営課題となっている。しかしながら、単純に同じ商品を同じ顧客に対して提供する場合、価格だけを上げることは難しい。消費者の感じる便益(利益)は、商品の価値/商品の価格であると考えられるためである。いわゆるコストパフォーマンスである(図表2)。
商品の価格のみを上げた場合、商品の価値が変わらなければ、分母だけが大きくなるので消費者の感じる利益は少なくなってしまう。値上げすると売れなくなるのは、この「コスパが悪くなる」ためである。そのため、商品の価格を上げるためには、分子である商品の価値も高める必要がある。ゆえに、価格転嫁を実現するためには、付加価値の向上、あるいは価値の丁寧な伝達もセットで行う必要があると言える。さらには、付加価値創造を行いやすい新たなマーケットを開拓することも検討できる。例えば、「吹き戻し」という口で吹くと音を出しながら伸びる玩具は、もともと古くから親しまれてきた子供向けの商品であったが、現在では健康や美容向けの商品として呼吸に意識を向けるという新たな付加価値が見出され、新しいマーケットの開拓につながっている。
コストの削減についても、物価高やエネルギーコストの上昇、最低賃金の引き上げもあり、単純にもっと安価な代替品を探してくるような形でコストを下げることは難しい。そのため、ビジネスプロセスを見直し、業務のスリム化等を行い、コストを減らすなり、あるいは従業員1人あたり、設備1台あたり、面積あたりの生産性を高めることでコストを下げるといったアプローチが求められる。
参考文献
チャールズ・A・オライリー、マイケル・L・タッシュマン,「両利きの経営:探索と深化の両立による持続的イノベーション」,『ダイヤモンド社』,2004年
- はじめに
- 好事例に見る流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(実践編)
- 流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(理論編)
- 流通・サービス業の現状と課題