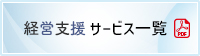~流通サービス業の実践的経営改善ガイド~
第1部:好事例に見る流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(実践編)
3.好事例を自社に落とし込むポイント
以上、ここまでは、事例の切り口から具体的な事例の紹介までを実施した。ここでは最後に、好事例を自社の経営に落とし込むために重要なポイントについてお伝えしたい。
どんなに良い事例であっても、あるいは自社に似た企業の成功事例であっても、それをそのまま真似して同じように実施してはいけない。一見、同じような状況、同じような事業を営む事業者であっても、自社とは全く同じではないのである。経営環境の分析などを丁寧に行えば、特に社内の環境は大きく違うことに気づくことができる。全く同じではないのだから、他社と全く同じアプローチを価格転嫁や生産性向上で取ったとしても、そのまま大成功、という形にはならないのである。
重要なのは、「なぜうまくいったのか」にフォーカスし、その理由を考えることである。その事例の取り組みが成功した理由を考え、その理由を自社にも当てはめることが重要なのだ。例えば、ある企業が「従来の商品よりも内容量が少ない商品を販売することで、商品の単価を安くしつつも1gあたりの単価を上げることに成功した」といった事例があった場合に、単純に「内容量の少ない商品を出せばよい」と捉えるのではなく、「なぜ、内容量を減らした商品が売れたのか」を考える必要がある。そしてその理由が「従来の商品は高齢化した顧客層には、量が多すぎた」ということであれば、この事例から学べる内容は「顧客のニーズに合わせた内容量の調整で単価を上げられないか」ということになる。決して単純に「内容量の少ない商品を販売する」ということではない。成功事例を見るポイントは「成功した理由」を考察することにあるのだ。
加えて、実際に事例を分析すると分かるが、自社内の状況(内部環境)と外部環境を考えた上で、複数のアプローチを上手に組み合わせながら経営改善を実施していくことが重要である。ここでは、プロダクト、プロセス、組織、マーケティングの4つのイノベーションの種類別に13パターンで経営改善アプローチを整理してきたが、新たなプロダクトを生み出すには組織やプロセスも見直す必要が出てくるなど、各イノベーションは深くつながっているのである。
また、革新的な取り組みを行いたい、イノベーションを起こしたいと思う場合は、少し視点を変える必要がある。イノベーションを起こしたいのなら、図書館に行って、見たことも無いジャンルの本棚にある本を読んでみると良い、という話もある。自分の思考の範囲外にある情報が、自分の頭の中の知識と融合したときに、全く新しいアイデアが生まれることもある。自分が今まで考えなかった視点で、事例を探してみても新しい発見があるかもしれない。話題になった経営学の理論、「両利きの経営®」においても、主力となる既存事業の強化と絶え間ない改善(知の深化)と、新規事業に向けた実験と行動(知の探索)を両立させることが、企業経営において重要であるとしている。事例を見ていく中でも新しい取り組みを意識して、今までとは異なる視点で事例探索をしてみることも重要である。なお、新しい視点で事例を見る場合も、「なぜうまくいったのか」の視点で考えることが重要である。

- はじめに
- 好事例に見る流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(実践編)
- 流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(理論編)
- 流通・サービス業の現状と課題