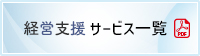~流通サービス業の実践的経営改善ガイド~
第1部:好事例に見る流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(実践編)
1.流通・サービス業の事業特性の検討
自社の経営改善を検討するうえで、同じような悩みを抱えた他社が、どのように課題をとらえ、改善したのか、事例から学ぶことは非常に有用である。事例を見る際には、以下の3つの事業特性に着目し、分析することで、自社にも落とし込みやすくなる。
なぜなら、事例を学ぶにあたっては、まずは自社に近い事例を学ぶことが重要となるからである。自社に近い事業者が、個々の課題に対し何を考え、どのような対策を行った結果、いかなる成果を上げたのかを知ることで、自社の取り組みの検討やチェックに活用することができる。以下の切り口から事例企業と自社の類似性を考えてみると良い。
Ⅰ.取引形態(BtoB,BtoC)
事業特性として、顧客が事業者(法人)であるのか、個人であるのかは非常に重要なポイントである。顧客数や客単価にも影響するほか、価格転嫁を行う際も、法人であれば営業活動の中での交渉が必要であるが、個人であれば個別に交渉することは現実的ではなく、WEBサイトやポスター等で告知する形となる。
Ⅱ.商圏特性
自分たちのビジネスが、広域商圏をターゲットとしたものであるのか、地域密着型のビジネスであるのかは、とりわけ流通・サービス事業者にとって、事業戦略を考える上で必要不可欠な要素であると言える。インターネットを使い、全国各地をはじめグローバルに商品を販売するビジネスモデルなのか、地元に直接販売する店舗を設け、地元顧客に密着しながら販売するビジネスモデルなのか、それによって経営改善に向けたアプローチが変わってくる。
Ⅲ.自社の強み(競争優位性の源泉)
自社の競争力の源泉がどこにあるのかは、類似事例を考える上で非常に重要な要素である。商品やサービスに独自性があり、他社が模倣できないものを持っていることが強みになっている場合と、従業員や組織体制、ビジネスプロセスが競争力を持っている場合では、アプローチが変わってくる。
また、流通・サービス事業者が経営改善を図っていく上では、まず、強みとなっているポイントを伸ばす、活用する方向性で検討を行うことが基本となる。商品やサービスも従業員も基本的には育てる必要があり、競争力の源泉となっている強みは一朝一夕で構築できるものではないためである。
さらに経営改善のアプローチとして、代表的なものを13パターンに整理した(第2部の理論編にて、詳しい理由を解説)。もちろん、他にも創意工夫によって多くのアプローチ・対応策があるが、これは事例を探し、考察する場合に使えそうな代表的なものとして整理したものである。
1.プロダクトイノベーションの取り組み
企業が新製品やサービスを開発し、差別化を図るアプローチ。
1.商品・サービスの希少性・独自性
提供する商品・サービスに希少性、独自性があり、他社が模倣困難なものを活用した取り組み。
2.新マーケット開拓
自社にとって、新しいマーケットや領域を開拓することで価格転嫁や生産性向上、売上・利益創出を行う取り組み。
3.ニッチ市場開拓
特定のターゲット顧客に向けたニッチな取り組みによって、競争が少ない市場を確保し、価格転嫁などを成しえた取り組み。
4.地域資源活用・地域連携
地域の特産物や地域ブランドを活用した取り組み、自治体と連携した取り組み、地域の観光資源を活用した取り組みで競合との差別化を図るものなど。
2.プロセスイノベーションの取り組み
製品やサービス自体の変化ではなく、それらの生産や流通の過程を改善し、効率化・コスト削減・品質向上を図るアプローチ。
5.事業・業務のスリム化
事業ドメインを再定義して経営資源を的確に配分したり、業務プロセスを見直したり、必要に応じてアウトソーシングを行い、組織や体制をスリム化することでコスト削減と人材活用(リソースの再分配)を行う取り組み。
6.DX・AIの活用
業務においてクラウドツールやAIを活用したり、RPA(Robotic Process Automation)のようなソフトウェアロボットを使い、定型業務を自動化したりするなど、DXを行うことで工数削減や生産性向上を図る取り組み。加えて、浮いた工数(人手)やDXによって得たデータを利活用することで、新たな商品・サービスの開発等を行い、競争力の向上を目指す取り組み。
3.組織イノベーションの取り組み
企業が自社の仕組みや構造、文化などを改革することで、新たな価値を生み出すアプローチ。あるいは、イノベーションを起こせる組織を構築するアプローチ。
7.組織改革
意思決定の速度を上げたり、現場での臨機応変な対応を支援したりするために現場の決済権を高めることや、組織を機能別に分ける形から事業部制に変える、組織の階層構造を見直し、フラット化するなど、組織改編によって生産性向上や柔軟な顧客対応を行うなどの取り組み。
8.他社・他業種との協創・協業
同業他社と競争にかかわらない部分(例えば、物流等)で協業を図り、互いの経営資源の不足を補完して新たな価値を生み出すことや、協業のプロセスを通じて新たなアイデアを取り入れること、コストを削減すること、他業種と連携することでお互いの経営効率を高めるような取り組み。
4.マーケティングイノベーションの取り組み
顧客ニーズを深く理解し、それに基づいて新たな製品やサービス、あるいは販売方法などを開発することで、顧客満足度と売上の向上を実現するアプローチ。
9.企業・商品のブランド力向上
自社のブランド力(認知・イメージなど)や商品のブランド力を高め、価格競争に巻き込まれないようにすることで顧客の獲得・維持と円滑な価格転嫁を図るような取り組み。
※中小・小規模事業者にとっての「ブランド」とは、一般的に認知度の高い「(高級)ブランド」ではなく、「この地域の、この商品・サービス」などといった限定的な範囲における高い認知度・イメージのことを指す。
10.顧客コミュニケーション強化
顧客とのコミュニケーションを強化することでニーズの把握を円滑に行い、新商品の開発や販売促進の高度化を行うような取り組み。
11.消費者への価値訴求
商品の価値を消費者に正しく、記憶に残るように伝達することで、商品の価値に合わせた価格転嫁を実施するような取り組み。
12.顧客ネットワーク活用
顧客のネットワークを活用した横展開や新規顧客の獲得を行うような取り組み。特にBtoCで事業を展開する事業者ではSNS等も含めた顧客とのつながりが会社としての競争力の向上につながる。
13.社会課題解決
自社の売上・利益向上と、地域や国の社会課題解決を同時に目指す(両立させる)取り組み。CSV(Creating Shared Value)経営と言われる事業活動を通じて社会的な課題を解決し、同時に経済的な利益も追求するような取り組み。

- はじめに
- 好事例に見る流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(実践編)
- 流通・サービス事業者の経営改善アプローチ(理論編)
- 流通・サービス業の現状と課題